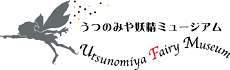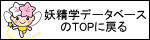12世紀後半から13世紀前半にかけての女流詩人。自作中で「私はフランス生まれのメアリー」と名乗ることから、フランス語でマリ・ド・フランスと言われているが、その生涯は定かではない。
彼女はフランス文学史上最初の女流作家だが、イギリスに移住して、プランタジネット朝の宮廷に仕えた。国王ヘンリー2世とその王妃アリエノールのブレーンとして働いた貴族階級の女性とも言われ、のちに尼僧院長となった。
その作品のスタイルはレー Laisと呼ばれる韻を踏む短詩で、もともとは口承による詩を書き記したもので、竪琴に合わせて旋律をつけて歌われた歌謡である。
とくに「マリ・ド・フランスのレー」The Lais de Marie de France は、ブルトン・レー Breton Lais (フランス語 Lais breton, Lais de Bretagne ブルターニュのレー)と呼ばれる。
12世紀に作られたというブルトン・レーは20篇ほどあるが、そのうちの12篇がマリ・ド・フランスの作品とされている。ブルトン・レーは中世フランス各地の方言に置き換えられ、13~14世紀には中世英語によるレーも作られた
レーのテーマは恋愛や騎士道などで、ロマンティックかつ神秘的、幻想的な情趣に満ちている。おおむねその舞台は森か荒野で、騎士が人気のない城に住む「妖精のように美しい」女性と恋に落ちたり、動物が人間の言葉を話したり、漕ぎ手のない船が走ったりするというもので、この世ならぬ異界の小道具が多く用いられている。
マリの作品は当時のアングロ・ノルマン語(フランス中・北部の方言)で書かれているが、題材や韻律にはギリシア・ローマの古典文学やケルト神話の影響が強く、現世からあの世への飛翔願望が現われている。
マリ・ド・フランスの手になる作品は、『ギジュマール』『エキタン』『ヨネック』『ランヴァル』『とねりこ』『二人の恋人』『ミロン』『ナイチンゲール』『オオカミ男』『すいかずら』『不幸な男』『エリデュラック』の12篇である。
騎士の愛と結婚をめぐる話が多く、欲望の自由を謳歌している(月島辰雄訳 『十二の恋の物語』参照)。そのうち、『ランヴァル』と『すいかずら』の2篇はアーサー王物語に関連した物語である。
作品のひとつ『ギジュマール』の最後にはこのような一節がある。「皆さまお聞きのこの物語から/ギジュマールのレーは作られたが、/竪琴やロッタで弾き語られ/その調べは耳に心地よく響く」(前掲書より)。
E.メイソンは、「マリのブルトン・レイ(引用者注:レー)の本質は、ブルトン(引用者注:ブルターニュ)起源というよりケルトそのものと言えよう。ブルトンとケルトの想像力には特異な夢想や魔法、神秘がある」と指摘している。
またマリ自身、レーは「妖精(フェアリー)が問題(プロブレム)を課す物語」と言っている。また、ジャン・フラピエは、「レ(引用者注:レー)ではほとんど常に主人公が、日常生活の世界を去り、選ばれた人のみ出入りを許される仙界、もしくは感情的別世界に入ることになる」と解説している(松原秀一 『中世ヨーロッパの説話』参照)。
ロンドンの酒商に生まれる。17歳ごろにはエドワード3世の第三王子のライオネル夫人の小姓であった。
1359年に百年戦争に参加し、フランスの捕虜となるが、英国に帰される。帰国後は宮廷人として働く。
1370年から数年間しばしばフランスを訪れる。このころ、『バラ物語』など宮廷恋愛を主題とした小説を訳す。
1372年にはしばしばイタリアを訪れ、ジェノヴァやフィレンツェに行き、イタリア・ルネサンスの影響を受け、とくにボッカチオにひかれる。それらは『トロイラスとクリセイデ』などに結実している。
後年『カンタベリー物語』(1387~1400年)を書き始め、死ぬまで書きつづける。この作品には彼の社会・人生への深い思索がうかがえる。
『カンタベリー物語』The Canterbury Tales(14世紀)にはギリシアのニンフと妖精との混同が頻繁にみられるが、これはニンフを妖精と初めに翻訳した『オデュッセイア』からの影響であろう。
例えば「貿易商人の話」では、「大勢の貴婦人たちを引き連れ/王妃プロセルピナを従えた/フェアリー国の王プルートー」となっており、ローマ神話のユピテルとケレスの娘プロセルピナが妖精の王妃になっているし、その夫のプルートーも地下の王であるのに、フェアリー国の王となっている。
この妖精王プルートーは、商人の妻マイが恋人と逢い引きしているところを、老人の商人ジャヌアリーの眼を開かせて見せてしまうが、プロセルピナは弁舌の才を与え、自己弁護をさせてまるく収める。
「サー・トパスの話」では、当時流行していた韻文ロマンスのパロディになっており、フランドルの騎士トパス卿が灰色の馬に乗り、槍を手にして走っているうちに、夢のなかで妖精の女王を恋人にする。
「バースの女房」では、アーサー王の時代にはフェアリーがいたが、このころにはいなくなり、「土地をまわる托鉢僧が婦女を犯す夢魔(インキュバス)になっている」と言っている。
チョーサーは冗談半分に妖精は何世紀も前にいなくなったといいながらも、風俗を写していくうちには世間好みの妖精を使わずにはいられなかったようである。
中世ロマンスとして英国全土に広がっていたアーサー王伝説を『アーサー王の死』Le Morte D'Arthurとして集大成した。
同名の人物は6人いたが、『アーサー王の死』の作者は、現在ではウォリックシャーのニューボールド・レヴィル出身のトマス・マロリーにしぼられている。
前半生は結婚したり従軍したり、ひとり息子に先立たれたりしたが、40歳ごろになると犯罪歴が多くなり、謀殺未遂、ゆすり、窃盗、強姦、強奪で告訴され投獄もされている。
『アーサー王の死』はマロリーが獄中で書いたものといわれる。最近ウィンチェスターで発見された写本の裏には「騎士囚人」a knight prisonerとあり「神よこの者を釈放し給え、アーメン」との直筆があるという。
英国ルネサンス期の代表的な詩人。ロンドンに職人の子として生まれ、ケンブリッジのペンブルーク・コレッジで学ぶ。レスター伯らとの交友からエリザベス1世の宮廷への出入りを望んだ。
1579年に出版した最初の詩集『牧人の暦』 The Shepheardes Calendarは傑作と評判になった。このころから、彼のライフワークともいうべき『妖精の女王』の執筆を開始している。
しかし、レスター伯の失脚により、宮廷への道が閉ざされたため、アイルランド総督グレイ卿の秘書としてアイルランドに赴任し、以後その生涯のほとんどをこの地で過ごした。
『妖精の女王』The Faerie Queeneは20年をかけた大作であり、存命中に4巻まで出版されたが、未完に終わっている。
その1~3巻が発表されると大変な評判となり、とくに、献辞を捧げられ、作中のグロリアーナ王女に擬せられたエリザベス女王はこれを非常に喜び、彼に年金を与えている。
しかし、アイルランドのコーク州の長官としては災難に見舞われ、1598年には自邸を住民に放火され、家族ともども難を逃れた。翌年、この事態を政府に報告するために趣いたロンドンで客死、ウェストミンスター寺院に埋葬された。
『妖精の女王』の続編の原稿は焼き討ちのさいに消失したとも言われたが、断片が見つかり、これが未完ながら第7巻として1609年に出版された。
英国の小説家、劇作家。オックスフォード出身で、ケンブリッジでも学ぶ。代議士として国政にも参画した宮廷人でもある。16世紀のケンブリッジ、オックスフォードで学んだ大学才人(ユニヴァーシティ・ウィッツ)の1人。
英国最初の小説といわれる『ユーフューズまたは才能の分析』Euphues, or the Anatomy of Wit(1579年)および『ユーフューズと彼の英国』Euphues and his England(1580年)の2巻の華麗な文体によって、繊細で機知に富み、やや冷たい感じのする彼の文体は「ユーフィズム」Euphuism(美辞麗句の語法と文体)として知られ、その後の散文に影響を与えた。
美しい叙情詩を挿入して初めて散文劇を書いたが、とくに英国喜劇の創始者と見なされ、「民衆の好みより審美的かつ知的な特質」をもとに喜劇を書いた。
英国特有のフェアリーの踊りや滑稽な身振りを持ち込んでいるが、作風じたいは非常に技巧的である。
アレクサンダー大王の恋を描いた劇『キャンパスピ』Campaspe(1584年)や、スペイン王フェリペ2世を題材にした作品『ミダス』Midas(1592年)、また牧歌劇『ガラテア』Gallathea(1592年)やレスター伯を諷刺した『エンディミオン』Endymion(1591年)等の寓意劇に多くの妖精を登場させており、初めて英国で散文劇に小さな妖精を導入した。
『エンディミオン』で妖精たちは、エンディミオンから受けた不当な行いを罰し、妖精生活への侵害にも罰を下している。眠っているエンディミオンを動かそうとしたコルサイティーズは、妖精たちに「青くなるまでつねれ。黒くなるまでつねれ」(『エンディミオン』4幕3場)と歌いながらつねられると、眠り込んでしまう。
また妖精の踊りやコミカルな身振りやものまねも、彼の戯曲の中に、次のように歌われている。「フクロウの鳴き声、蛙のガァガァ鳴く声、蛇のシューシュー鳴く音、狐の吠え声、そして魔女の歩く音」(『ガラテア』2幕3場)。
ハンプシャーのエルヴェサムを巡幸中のエリザベス女王に捧げた余興劇(Pregreses, at Elvetham in Hampshire、1591年)では、オレオーラという名で、フェアリー女王が白銀の杖を手に花輪で飾られて姿を現し、うやうやしく女王陛下にご挨拶するが、その王冠はオーベロン王に与えられたことになっている。
英国の劇作家、小説家、詩人。16世紀末の大学才人(ユニヴァーシティ・ウィッツ)のひとり。ノリッジ出身で、オックスフォードでも学んだ。グリーンの生涯は短く、放蕩の末に死んだが、多くの作品を著した。
エドワード1世の若き日の恋を題材にして戯曲を書き、中世の魔術師『僧ベイコンと僧バンゲイ』Friar Bacon and Friar Bungay(1594年)も描いた。
小説『パンドストー』Pandosto(1588年)は、シェイクピアの『冬物語』の粉本となる。パンフレットには、ジョン・リリーの『ユーフィーズ』Ephuesの続編、『ユーフィーズのフィロータスへの叱責』Euphes, his Censure to Philautus(1587年)があり、そのなかでリリーと同じく、妖精たちを登場させている。
パンフレットのひとつ、『無数の悔悟によって購われたグリーンのわずかに価値ある機知……生前に書かれ、遺言により1592年に出版される』(Greenes Groats-Worth of write, bought witte a million of Repentance...written before his death and published at his dyeing request 1592)の中の1節に「いや、あなたのご判断には賛成しかねる。そう、かく言うわたくしはこの時代のいかなる人より「フェアリーの王」<デルファガス>として名高いのだ」とある。
この2年後に『ジェイムズ4世』(完全な題は「フェアリー王オボラムによって引き起こされる愉快な喜劇」)を加えた、フロデンで没したジェイムズ4世のスコットランドの歴史」(The Scottish Historie of James the Fourth, slaine at Flodden, Entermixed with a pleasant Comedie presented by Oboram King of Fayereies、1598年)の戯曲で、妖精王を<オーベロン>と名づけ、「ボアン、お前に言おう。オーベロンこそは静寂の、喜悦の、利益の、満足の、富の、名誉の、そして全世界の王なのだ」(1幕)としている。この劇の幕間に妖精たちを登場させ、踊らせている。
シェイクスピアの『夏の夜の夢』はこの作品に負うところが多いとチャートン・コリンズは言うが、両者の妖精王オーベロンには、性質の相違はあるにせよ、いわばシェイクスピアのオーベロンの原型とみられよう。
また『愚行為への決別』Farewell to Folly(1591年)や自伝的な『詐欺方法百般』Conny-catching(1591~92年)、『一文の知恵』A Groats Wroth of Wit(1592年)があり、前者は当時のロンドンの暗黒面を伝える資料で、後者はグリーンの私生活が描かれているが、またシェイクスピアを「われらの羽根を使った美しいカラス」と言っており、マーローの悪口も書いてあるので知られている。
エリザベス朝時代最大の劇作家、俳優、詩人。十分な記録資料が現存せず、その生涯は推定の域を出ないが、4月23日誕生、26日受洗の記録はある。
イングランド中部の町ストラットフォード=アポン=エイヴォンに生まれ、商人で町の有力者(一説に手袋商人)の父ジョンと、母のメアリー・アーデンの8人の子どもの3番目で長男。大学には行かず、地元のグラマー・スクールで学ぶ。18歳で8歳年上のアン・ハサウェイと結婚、1男2女(男女の双子)をもうける。
1585年に旅の一座とともに、単身ロンドンに出る。7年後には「何でも屋」の評が示すように、劇場の馬番から身を起こし、1590年前後には、役者と芝居の脚本家を兼ねる。
ペストの流行でロンドンの劇場が一時閉鎖された後、1594年劇場が再開されると、「宮内長官一座」(後「国王一座」)の主要俳優兼脚本家となり、1599年に「地球座」を「劇場」の古建材で建て、持ち主だったバーベッジの息子らと共同経営者兼株主となる。
「地球座」は、1613年『ヘンリー8世』上演時の祝砲から出火して消失、翌年に再建される。しかし、劇場を悪の温床とみる清教徒により、1644年に破壊される。
1612年ごろ、ストラットフォードに帰り、4年後の4月23日に、1597年に購入した新宅「ニュー・プレイス」で死去、「ホーリー・トリニティ教会」内に埋葬される。
シェイクスピアはロンドンで活躍中の27年間に、37篇の戯曲と7篇の詩集を残す。その中で『夏の夜の夢』(1595~96年)、『ウィンザーの陽気な女房たち』The Merry Wives of Windsor (1600~01年)、『ハムレット』Hamlet (1600~01年)、『マクベス』Macbeth (1605~06年)、『テンペスト』(1611~12年)等、代表作には、登場人物の内面や運命を演じるかのように、妖精、魔女、亡霊ほか超自然的な生き物が重要な役割を果たしている。
エリザベス朝時代に流行したパンフレット『ロビン・グッドフェロー、その悪ふざけと陽気ないたずら』Robin Good-Fellow ; his Mad Pranks and Merry Jets (1584年)や、民間伝承の妖精に関する知識に加え、レジナルド・スコットの『魔術の発見』 The Discoverie of Witchcraft (1584年)等の書物の知識、それに自らにそなわった演劇本能と想像力で、独自の妖精像とその世界を創造した。
シェイクスピアはさまざまな国の伝承や要素を、ひとつの坩堝(るつぼ)の中で溶け合わせ、独自の容姿と性質をそなえた、彼自身の妖精をつくりあげた。
英国の妖精がもつふたつの本質的な性格、第一に妖精の神話的な起源と、人間に理解できない恐ろしい能力をもつという妖精の民俗的な性格。
第二に中世ロマンスからくる妖精の世界、王と女王と宮廷といった上流社会のパロディとしてのフェアリーランドの住人という存在。
これらを混ぜ合わせ、それまでにない存在をつくった。それまで人々のあいだで、醜く恐ろしい存在だった妖精たちを、バラの花の虫を取り、月夜の調べに合わせて踊る「自然の精霊」のような性質にし、ドングリの殻にもぐり込むような「小さく美しい容姿」を与え、「人間に親しい性質」をもつ存在にして戯曲に登場させたシェイクスピアの功績は大きい。
エリザベス朝の詩人。シェイクスピアと同郷で、1歳年長である。裕福な商人の子として生まれ、のちヘンリー・グッデール家に仕え、その娘アンを愛する。詩集『理想』 Idea (1593年)などで、アイデア(Idea)と呼ばれ歌われている女性が、このアンである。
長い生涯において、さまざまな種類の詩を書いていた。英国の風土記ともいうべき長詩『大幸の国』 Poly-Olbion (1612~22年)では、当時一躍ヨーロッパ最強国となった祖国の栄誉を讃えて、評判となった。そのほかに、ソネット集『理想の鏡』Idea's Mirror(1594年)がある。
戦争詩『アジンコートの戦い』 The Battle of Agincourtの中で、物語詩『ニンフィディア』(1627年)を書いている。この作品はスペンサーの『妖精の女王』(1596~1609年)に類似しており、オーベロン王とマブ女王の妖精王国の中に、『夏の夜の夢』のように、小さい妖精たちが登場する。
英国の詩人、批評家、劇作家。誕生前に父を失ったベン・ジョンソンは、煉瓦職人の継父に育てられ、ウェストミンスター校に学び、歴史家、古典学者のキャムデンの教えを受けた。
1591年から大陸に従軍、1597年にヘンズローに雇われ、俳優から劇作家に転じて台本作家として活躍した。最初の桂冠詩人の栄誉もかち得た。学才、識見ともに文壇の第一人者となり、気質喜劇(Comedy of Humours)の確立者といわれる。
『ボルポーニまたは狐』Volpone, or the Fox(1607年)、『十人十色』Every Man out of his Humour(1598年)、『錬金術師』The Alchemist(1610年)等、市井生活の冷酷な写実と苛烈な諷刺の作品を書いた。
1605年より王室お抱えの作者となり、宮廷仮面劇や牧歌劇には、魔術やフェアリー伝説の世界を豊富にとりいれ、シェイクスピアの衣鉢を継いだ。
『女王たちの仮面劇』Masque of Queensで魔術に関する知識と共感を示した。
また1610~11年のクリスマスの祝祭には、仮面劇『妖精王子オーベロン』Oberon: The Fairy Prince(1611年)を上演した。劇の主題はアーサー王からジェイムズ1世までの理想的な支配者を、オーベロン王が祝福するスペクタクル劇である。この劇ではイニゴ・ジョーンズ考案の装置が用いられた。
デヴォンシャー・コレクションに現存する素描では、岩のドームに小塔のついた城がそびえ、「岩の扉が開いて妖精の王の壮麗な宮殿が現れる」とある。
妖精のデザイン画には、鳥に似た白と金の翼をつけ、イルカのような尾と腰に草の蓑をつけ、魔法の杖を手にしたオーベロン王が、3匹の白熊に曳かせた車で、妖精の騎士を従えている。
森の精たち、シルヴァン、シレーヌス、サテュロスが、機械装置で「天空」を象徴する天井からクレーンで降りたり、雲をかたどったゴンドラの宙乗りで、舞台を横切ったりしたらしい。
ジョンソンは仮面劇の序詩として書いた作品で、ロビン・グッドフェローを書いている。また『悪魔は間抜け』The Devil is an Ass(1616年)では、チャップブックのフライアー・ラッシュの物語を扱っており、鬼火であったラッシュを、ロビン・グッドフェロー的な物語に描いている。
シェイクスピアの妖精女王ティターニアに対し、ジョンソンは『サテュロス』The Satyr(1603年)で、妖精女王を「マブ」として登場させ、「もしも田舎の女中めが、腰かけを汚れたままにしておけば、女どもをつねるのは、マブ女王さま」と言わせている。
1637年に死去、ウェストミンスター寺院に葬られ、墓碑銘には「ああ、たぐいまれなるベン・ジョンソン」と刻まれている。
英国の牧師。学識豊かな解剖学者でもある。著書『憂鬱の解剖』The Anatomy of Melancholy(1621年)で知られる。この本は、英国散文の傑作といわれ、奇書珍籍よりの博引旁証によっており、雑学の宝庫の観がある。18世紀のジョンソンやラム、19世紀浪漫派の詩人ジョン・キーツらが愛読した。
なかでもキーツは、この本に出てくるフィロストラトスの書いた若者メニプス・リシウスと美しい蛇女レイミアの誘惑、結婚、正体暴露の話をもとに、長篇物語詩『レイミア』Lamia(1819年)を書いている。
ロバート・バートンはその著書の中で、超自然の生きものについて種々言及しているが、とくに妖精については次のように言っている。
「フェアリーたちはその昔、多くの迷信によって愛されていた。人々は家の中を綺麗にしたり、バケツ1杯のきれいな水や良い食料や、そうした類のものを用意したりすれば、フェアリーにつねられないばかりか、靴の中にお金を見つけたりするし、またやる仕事が順調に運ぶと信じていたのである。
野原や牧草地で踊るのはフェアリーたちであって……、その広い野原の跡には、よく知られているように緑の輪を残す。ある者はこれは流星が落ちてできるのだ、と思っているし、また偶然に地面に草が茂ってできる現象だともいわれており、年とった女とか子どもたちが、よくこれを見つける。
パラケルススは、ドイツのいろいろなところで、フェアリーが、2フィートの長さのコートを着て歩いているのを、いつも見かけたと記している。
身体の大きな種類はホブゴブリンとかロビン・グッドフェローとか呼ばれており、迷信の時代には、ミルクを1杯持っていってやれば、小麦や大麦を挽いたり、木を切ったり、いろいろな勝手仕事をやってくれたものである」。
この記述は民間伝承の妖精のことであり、ロバート・バートンは妖精に関して興味は抱いているが、妖精話は迷信だとみていたことがわかる。
エリザベス朝の詩人。デヴォンシャーの町タヴィストックに住んでいた。この地方は銅や錫の鉱山で知られ、地下にピクシーやノッカー、スプリガン等コーンウォールの妖精が棲むと信じられ、民間伝承が豊富で、それを詩に歌った。
ブラウンはスペンサーの熱烈な参拝者であり、ドレイトンの『ニンフィディア』の影響を受けて、『ブリタニアの田園詩』Britannia's Pastorals(1613~28年、3巻)を書いている。
ブラウンの妖精は、ドレイトンの妖精より大きめで、ハサミ虫のかわりにネズミに乗っている。
地下に妖精の宮殿があるというブラウンの設定は、コーンウォールに伝わる民間伝承を忠実に守ったものである。
その詩の一説に「岩石を彫ってつくった部屋の開き戸は真珠貝、蝶番と釘は金、豪華な部屋には掛け物がさがっている」とあり、壁の絵は「博識のスペンサーが、小さな丘の上でペンを進める様子が見える」と『妖精の女王』の中で描いている。スペンサーの肖像画が、ブラウンの歌う妖精の部屋に掛かっていることは興味深い。
「白いスープのなかに煮えているのは
肥らせたバッタ、
アリの丸焼きにザリガニの卵が5つ
ネズミの乳房、クマンバチの足2本
よく浸けたのはオリーヴならぬリンボクの実、
次にはコウモリのつま先が出され、
ソースをかけた3匹の蚤、塩漬けのキリギリス、
そして最後にネムリネズミの美味なる顎」
ブラウンの『ブリタニアの田園詩』を、へリックの詩が継承したという説や、反対にへリックの詩が出された後にブラウンが出ているので、ブラウンがヘリックの影響下にあった、という説などさまざまにいわれている。
ブラウンとヘリックの妖精の描写は、「キノコのテーブル」や「若露の小粒の真珠」など、確かに共通点がある。
これらの描写は後世のヴィクトリア朝の妖精画家たち、リチャード・ドイルやフィッツジェラルドが妖精をカンヴァスに描く際にも用いられている。後年のミルトンやキーツの詩作品にも、影響を与えている
エリザベス朝の詩人。ロンドンに生まれ、王室御用の貴金属商であった叔父の店に年季奉公した後に、ケンブリッジに学ぶ。
母親の死後、デヴォンシャーのバッキンガム公の礼拝堂の専属司祭をしていたがその職をやめ、ロンドンの都会からコーンウォール半島の田園デヴォンシャーのディーン・ブライヤーの司祭館に住み、緑の丘陵地帯や美しい田園の中で超自然の生き物たちと交流しながら詩作を続けた。
ヘリックの想像力は妖精国の、主としてオーベロンに向かい、次々と作品を書いていった。
「オーベロンの祝宴」「オーベロンの宮殿」「妖精の神殿 あるいはオーベロンの礼拝堂」「物乞いからフェアリーの女王マブへ」など、オーベロンを中心とした妖精王国の長篇を書く構想があったようである。
英国の詩人、劇作家。ケンブリッジで、英語とラテン語の詩人として認められた。ベン・ジョンソンと交友があった。
牧歌喜劇『アミンタス、あるいは不可能な持参金』Amyntas, or The Impossible Dowry(1632年頃)、『詩神の鏡』The Muse's Looking-Glasseや劇的対話『アリスティプス』Aristippus, or the Jovial Philosopher(1630年)など短い生涯だが多量の作品を残している。
ランドルフの作品のひとつ、『アミンタス』には妖精が登場する。この作品はイタリア風の田園劇に近いが、英国的ともいえる新鮮な筋を入れている。
「無頼な少年ドリラス」は「ファンタスティックな羊飼いで、フェアリーの騎士」であるジョカスタスや田舎の若者たちの一隊を率いて、人々を騙してまわる。
第1幕では「愚かな預言者」モプサスが、テスティリスに思いをよせているので、ジョカスタスはモプサスに向かって、もっと身分が高い人に目を向けさせようと努める。
ジョカスタス
「もっとましな相手を選べばいいのに、
フェアリーの貴婦人を愛しなさいよ!
そうすれば高貴なオーベロンが君の味方になるだろうし、
美しいマブの女王が名誉ある乙女を選んでくれよう」
モプサス
「なんだって?ジョカスタス、
人形と結婚? 光の中の塵といっしょになれと言うのか?
クルミの殻の中で妻を探すのか? 声しか聞こえぬ
ブヨに求婚しろというのか? だめだ、ジョカスタス、
血も肉もある身体が、テスティリスが欲しいのだ。
フェアリーなんか勝手にしろだ!」
第3幕では、ドリラスはオーベロン王に化け、友人のジョカスタスの果樹園からリンゴを全部盗んでしまおうとする。ドリラスはフェアリーの群れとともに登場する。
ドリラス
「歩き方も、ピグミーの若い王子のようだろう?
……フェアリーは、子どもを連れたニンフのように欲しいものを手に入れる。
さあ、ぼくが教えた不思議な言葉で、フェアリーの輪唱を歌ってくれ」
『アミンタス』に登場するフェアリーたちは、人間と同次元で描写されるが、しかしシェイクスピアのころのロマンティックな魅力を失って、「優雅な無頼の徒」になり下がってしまっている。
英国の文人。もともと医者で、オックスフォードやその他の大陸の諸大学で医術を修め、1637年以後、ロンドンの北ノーリッジに住む。
ラテン語や奇警な言い回しを使う特色ある文体で、当時スタイリストとして知られていた。博学多識、各方面の著述があり、代表的なものに信仰と理性との問題を取り扱った告白録『医師の宗教(レリギオ・メディチ)』Religio Medici(1643年)があり、その中で彼は魔女の存在を信ずることを書いている。
「……多くの学識ある人たちが、自分の形而上学も被造物者の階梯をも忘れてしまい、精霊の存在をどうして疑問に思うようになったのか――他の人はいざ知らず、自分はつねに魔女の存在を信じてきたし、いまはこれを知っている。
魔女を疑う者は、それを否定するに止まらずして、ほかの精霊をも否定することになり、その結果として間接には、一種の不信者、否、無神論者たらざるをえないのである」。
このような信念が、この時代のいく人か最高の思想家たちによって大胆に宣言されている。またトマス・ブラウンは、鉱山にはゴブリンが棲むと信じていたらしい。
この他に警抜な死生観を述べた作品、『壺葬論』Hydriotaphia : or Urne Buriall(1658年)などがある。
英国の詩人。純粋なピューリタン(清教徒)であり、イングランド教会(国教会)の改革を不十分として、さらなる改革を主張した英国プロテスタント教徒である。
父は富裕な清教徒の公証人であった。ケンブリッジで学ぶが、学芸に全力を注ぐ意志が強くなり、父の期待した国教会牧師を断念する。
ミルトンの最大の傑作『失楽園』Paradise Lost(1667年)にも、天使や悪魔の他にフェアリーも登場する。
「……そのインドの山の彼方に棲む
ピグミーの一族、あるいはフェアリー・エルフが、
真夜中の森陰や泉のそばで、盛大に開く酒宴のこと、
帰宅の遅れた百姓がそれを見たと言うが、あるいは夢を見ていたのか……」
(1巻780~784行)
この詩行は、シェイクスピアの『夏の夜の夢』の一節に似ていよう。
ミルトンは出身の中部オックスフォードシャーのフォレスト・ヒル周辺の地方に伝わる妖精伝承を知っており、初期の作品『大学休暇中の練習』(1628年)などに、民間伝承の妖精たちを登場させている。
1632年ごろに書かれた『ラレグロ(快活の人)』L'Allegro、『イル・ペンセロソ(沈思の人)』Il Penseroso、『コーマス』(執筆1634年、出版1637年)では、父の別荘があったバッキンガムシャーのホートン村に伝わる民間伝承話から、マブ女王やロビン・グッドフェローなどを取り上げている。
そしてミルトンは「ラバー・フェンド」lubbar-fendという独自の妖精を歌っている。「フェンド」は古代英語で「敵」の意味で、悪魔や悪霊、ドラゴンなどを指すが、ここから農家に現れ、粥一杯で麦打ちなど、人の手助けをするゴブリンをつくりだした。
英国17世紀中葉の女流詩人。ドレイトン、ヘリックやW.ブラウンを模したと見られるフェアリー詩の連作がある。
そのひとつ『地球の中心なるフェアリー国におけるフェアリー女王の気晴らしと冒険』The Pastime and Recreation of the Queen of Fairies in Fairy Land, the Center of the Earthにはフェアリーの調度品が緻密に描かれ、ラムの賛辞と対照的にピープスに批評されたその悪口の一語、"A mad conceited, ridiculuous woman"が有名である。
「フェアリー女王は、生まれおちるや、地球の環の中心の、
大いなる王国を継いだ。そこには多くの泉が湧き、小川は流れ、
さざ波は女王の眩い光できらめく……山々はみな、まじり気なしの純金、
石は見るも全きダイアモンド、ルビーやサファイアの石切場が
そこここにたくさん、水晶やアメジストも数多く……」
妖精の街は、「脳髄」で、硬膜と柔膜の二重の城壁に取り巻かれているとなっている。
すなわちそこでは、人間の空想は妖精が描く絵となっており、描写の筆は微に入り細をうがっており、かえって妖精の世界は、人間のミニチュア化になり、宝石で飾られており人工化されている。
英国最大の諷刺作家。アイルランドのダブリンに生まれ、キルケニー・グラマー学校からトリニティ・コレッジに入る。在学中に学業を怠るが、特別に学位を授けられる。
1690年にウィリアム・テンプル卿の秘書となり、そこに出入りする政治家たちを知る。親子でテンプル家に世話になっていたステラ(イサー・ジョンソン)と親しい関係を持つ。
1699年テンプルの死によりアイルランドに帰り、牧師となったり、1713年には聖パトリック教会の牧師となったりしたが、彼の野心は政界にあり、たびたびロンドンを往来した。
1704年『桶物語』A Tale of Tubeは、親譲りの上着を争う3人の息子に仮託して、カトリック派、プロテスタント派、国教会派を諷刺したものである。アン女王の死後は立身の望みを失い、アイルランドに隠退したが、なお諷刺の精神は衰えず、本国のアイルランド政策を糾弾した。
諷刺文学の傑作である『ガリヴァー旅行記』Gulliver's Travelsは1726年に書かれるが、まず第1部は船医ガリヴァーが、難破して小人の国リリパットの国に着く。
住民の内乱、隣国との戦争、国王の威儀などが書かれているが、小人の国はすべて英国になっており、英国の諷刺の意図は明らかである。2部はブロブディングナグという大人国。
第3部はラプュータという浮島。四部は馬と人間(ヤフー)が逆になっている国である。ケルト文学の「ブラン」のように島巡り(インムラマ)を思わせるが、奔放な発想による、架空の国と人民に対する諷刺文学である。
英国の詩人。ロンドンのカトリック教徒の裕福なリンネル商の家に生まれ、ウィンザーのビンフィールドに住む。
虚弱な体質だったポープは正規の教育を受けられず、独学でスペンサーやドライデンなどの韻律法を学んだ。12歳のころから詩作を試み、16歳で詩集『牧歌』Pastralsを発表した。
また、ホメロスの『イリアス』と『オデュッセイア』を翻訳している。ポープの詩の中で最も優れているのは諷刺詩Satireであり、『髪の毛盗み』(1712年)はその傑作といわれている。
評論には『愚人列伝』The Dunciad(1728~42年)、『人間論』An essay on man(1732~34年)がある。
古典的な素養を基礎に、ロマン主義的かつイギリス独特の幻想的な雰囲気をたたえた詩は、後世の多くの詩人や画家に影響を与えた。
英国の文豪、サミュエル・ジョンソンはリッチフィールドの書店の家に生まれ、オックスフォードのベンブルーク・コレッジに学ぶ。
しかし貧困のため学位を得ずに卒業。その後、小学校の補助教師やバーミンガムの出版社の手助けをする。
1735年に20歳年上の未亡人と結婚。私塾を開くが、経営に失敗。
1737年にデヴィッド・ギャリックとともにロンドンに出る。『ジェントルマンズ・マガジン』に議会記事を寄稿するかたわら、『ロンドン』London(1738年)、『人間の欲望の空しさ』The Vanity of Human Wishes(1749年)などを書く。
1750年、雑誌『ランブラー』The Ramblerを編集する。
ジョンソンはさまざまな業績や作品を残したが、なかでも8年の歳月をかけた『英語辞典』A Dictionary of the English Language(1755年)の独力での編集、また1765年の『シェイクスピア全集』の編集、52人の詩人の伝記を書いた『詩人伝』The Lives of the Poets(10巻、1779~81年)が代表的なものである。
『英語辞典』では「ローヘッド・アンド・ブラディー・ボーンズ」(「生首に血だらけの骨」の意)を「子どもを脅すのにつかわれる妖怪の名前」と定義して、J.ドライデンとJ.ロックから例を引いている。
また「シェイクスピアの時代には妖精というものが盛んに流行しており、広くゆきわたった伝承を通して、人々は妖精を、なじみ深い存在として受け止めていた。そしてスペンサーの詩は、そうした妖精たちを偉大なものにしたのである」と述べている。
妖精物語『ファウンテンズ』The Fountainsでは、少女フロレッタが鷲に追われた小鳥を助ける。
小鳥は「興味本位ではなく、人間が真心で助ければ魔法が解ける」という呪いにかかった「青い岩の妖精リネット」で、フロレッタの助けで、元の人間の姿に戻る。お礼に願いをかなえる約束をする。
妖精リネットは、洞窟に連れてこられ、望みを言いながら水を飲むと、その願望が次々とかなう。
フロレッタはまず「美しくなりたい」という願いをし、泉の水を飲む。すると輝く瞳とバラ色の頬の美人となり、男性が現れ、愛の告白をする。この甘い水は飲みすぎると、逆効果になり、美は保てず、服もボロボロになる。
今度は「金持ちになりたい」という願いをし、苦い水を飲むと、家中が金・銀・宝石でいっぱいになる。そのため人々の、嫉妬やねたみを買い、富の空しさを知る。次に「知恵」をもらうが、これも長く続かない。
年をとったフロレッタは、妖精リネットの最後の口づけを願い、静かに自然に帰ってゆく。「人間の欲望の空しさ」を、妖精を使って、象徴的に書いたような物語である。
英国の詩人、画家。ロンドンの靴下商の子として生まれ、正規の学校には行かず画塾に通い、彫版師ジェームズ・バジールの内弟子となる。
自分の彩色版画をつけた『無垢の歌』Song of Inocence(1789年)、『経験の歌』Song of Experiences(1794年)をはじめ、神話的世界を描いた『ユリゼン』The First Book of Urizen(1794年)や『四つのゾア』The Four Zoas(1795~1804年)など象徴を通して描いた幻想に満ちた神秘的な作品群、『予言の本』Prophetic Booksなど一連の作品がある。
1800年、ブレイクが40歳を過ぎたころ、友人ヘイリーの招きでサセックスのボグナー近郊のフェルパムに居を移した。
そこで妖精の葬式を見たことを、ある婦人に話した。「キリギリスの大きさで、草色と灰色の生き物の行列が、バラの花びらの上に死骸をのせ運んでいました。一行は歌いながら死骸を埋めると姿を消しました。あとで思うと、あれは妖精の葬式でした」。
ブレイクが見た妖精たちは、キリギリスなど昆虫に似た小さな妖精で、1785年ごろにシェイクスピアの『夏の夜の夢』から題材をとり、ブレイクが描いた妖精画《踊るフェアリーたちとオーベロン、ティターニア、パック》が思い起こされる。
妖精王と女王の仲直りを祝して、パックのカスタネットの響きに合わせ、4人の妖精の侍女たちが、星空の下、草原の妖精の輪の上で踊っている場面である。
この他ブレイクはミルトンの『ラレグロ』に出てくる妖精ラバー・フェンドをもとにした妖精画《ゴブリン》を描いている。
ブレイクの考えていた妖精は、蝶のように小さく、羽をもって飛び回り、歌い踊り、繊細なものだった。
詩の中で妖精が詩人に向かって、「おお、妖精の主人よ」と言い、詩人と妖精のつながりが、主人と従者の関係になっている。
『ロセッティ写本のなかの初期の詩』の一節で、ブレイクは妖精を歌っている。
「妖精が私の膝の上ではねた、楽しげに歌い踊りながら――
私は言った『お前たち、指輪やピンやネックレス、
そういう類いの婦人用の張りつけ細工、婦人の姿を飾る装身具、
つまらぬ金めっきの害虫どもよ!』」
妖精は泣きながら私の膝の上に倒れると、涙声で静かにこう答えた
「貴方はご存知ないのです、妖精の御主人さま!
私たち妖精だって、心の嵐に堪えることのできない
婦人の姿を隠すものは何であれ、
どんなに嫌いで憎らしく思っているかを……」
ここにはシェイクスピアの影響がうかがえると同時に、ブレイクにとって妖精は、とらえて命令し、意のままに動かせる精霊の存在、として理解していたようである。
これは見方を変えれば、ブレイクが自分自身を、精霊を自在に操れる魔術師・預言者(1799年より28年間、ブレイクはアーキドルイド(ドルイド司祭長)であった)として考えていたことを示していよう。
スコットランドの歴史小説家、詩人。弁護士の子としてエディンバラに生まれる。幼いとき、小児マヒで足が不自由となり、読書や母親の話を聞くことを好む少年だった。
1792年に弁護士となる。英・仏・独の語学に堪能で、当時ドイツで流行っていた新しいバラッド、ゲーテの『魔王』を英訳する。
作品には『湖上の美人』The Lady of the Lake(1810年)、『アイヴァンホー』Ivanhoe(1819年)、『ケニルワースの城』Kenilworth(1821年)、『ロブ・ロイ』Rob Roy(1818年)など歴史小説が多く、これらは30冊に及び「ウェイバリー叢書」といわれる。
トマス・パーシーの『古謡拾遺集』を少年時代に読んで刺激を受け、スコットランド地方の古い伝説物語やバラッドに興味を抱き、余暇を利用して旅をし、スコットランドの国境地方に伝わる昔話を収集、リッズデールの未開地方へは、7度も足を運び、部族の古老が歌う古い歌謡や昔話、伝説などを蒐集し記録した。これらは『スコットランド国境地方の吟遊詩歌集』The Minstrelsy of the Scottish Border(1802年、3巻)に集大成されている。
この注を理論として独立させる意向があり、死の2年前に、義理の息子に宛てた10通の書簡形式の『悪魔学と魔術に関する書簡集』Letters of Demonology and Witchcraft(1831年)を刊行する。
このなかには妖精神話、妖精と魔女信仰など、妖精の淵源と特色などがまとめられ,古物収集家(アンティクワリアン)antiquarianとして、大きな足跡を残している。
『スコットランド国境地方の吟遊詩歌集』は、「歴史的バラッド」「ロマン的バラッド」「現代物語詩」に分かれ、『ロビン・フッド』『詩人トマス』や、『人魚』『バンシー』『水棲馬』などの物語詩が多数収められている。
「浪漫的バラッド」項目の『タム・リンの物語』につけられた「民間信仰における妖精」という注釈などは、妖精学研究のうえで貴重な画期的記録であり、後の時代のW.B.イェイツやダグラス・ハイドの研究をはじめ現代のフォークロリストにとっても民間伝承研究の基礎のひとつとなっている。
スコットランドにおける妖精の概念や、スコットランド地方の民間に伝わる妖精信仰のあり方や、さまざまな妖精物語、例えば「妖精の騎馬行(騎馬行列)」「妖精の棲み家」「取りかえ子」や「妖精の呪文」などについて記し、また「レイミア」「ドエルガー(ドゥアガー)」「赤帽子(レッドキャップ)」「ミューア家の茶色男(ブラウンマン・オブ・ザ・ミューア)」など多くの妖精の記述がある。
「万象に神性があると信じている人にとっては、妖精や亡霊、超自然の生きものが存在すると認めるのは容易なことである」という考えにスコットは根差している。この妖精観はケルト的であり、ドルイドの生命の輪廻説に近いものであろう。
英国の詩人、批評家、哲学者。デヴォンシャーの牧師の子に生まれ、幼少のころ父を失う。ロンドンのクライスト・ホスピタルに学び、ケンブリッジのジーザス・コレッジに入学。
しかし中途でケンブリッジを去り、第15騎兵連隊に入るが、数ヶ月後にまたケンブリッジに戻る。
1795年にアメリカに新しい村パンティソクラシーをつくる理想に燃え、同志で詩人ロバート・サウジーの妹と結婚したが夢は破れる。
この年ワーズワース兄妹と出会い、友情を深める。1798年にワーズワースとふたりの共作詩集であり評論集の『叙情小曲集』Lyrical Balladsが生まれる。
コールリッジの作風は幻想的だが、1797年作の『クブラ・カーン』Kubla Khanも『クリスタベル』Christabelも未完である。
完成している長篇詩『老水夫行』The Rime of The Ancient Mariner(1798年)は代表作で、友人の画家のクルックシャンクが話した「人影が見える骸骨船を見たという不思議な夢」に基づいている。難破船から戻った老水夫が、結婚式に行く途中の若者に聞かせた身の上話になっている。
船が南極の海に入り氷に閉ざされたとき、1羽のアルバトロス(アホウドリ)を殺す。この罪深き行為に海の守護妖精が復讐し、船は呪われて赤道で停止し、乗組員全員が死ぬ。
海蛇の美しい群れや幻の船が現れる幻想的な世界が、詩人独自の言葉の魔術によって現出されている。ただひとり生き残った老水夫が乗る船を海に操るのは、「南極の精霊の仲間である守護のデーモンたち、宇宙の原素の目に見えぬ生きもの」であると、詩人は自注で書いている。
土地にはおのおの守護精霊が棲むと考えるコールリッジは、故郷デヴォンシャーの妖精を『ピクシーの歌』Song of Pixies(1793年)で歌っている。
デヴォンシャーのオッター川が流れる土手のほら穴「ピクシーのほこら」(ピクシー・パーラー)にはピクシーたちが棲み、月夜の原でマドリガルを歌い踊るという伝承をもとに、自分の幼少の体験を交えて書いた、最初の超自然の存在を歌った詩である。
しかしコールリッジは、コーンウォール地方の鉱山妖精ピクシーといっしょに、古典神話のニンフも詩のなかに登場させている。
「婦人たちよ、小さな部屋へようこそ、
そこは汚れのないピクシーたちが住むところ、
だが、われらが妖精の女王という優しいニンフたちよ、
あなたのお出ましには、どういう挨拶をしようか」
『クリスタベル』は、中世の森と城に繰り広げられる一種の韻文ロマンスだが、この森の精霊ともいえる魔性の女性が登場する。
コールリッジは自然の中には、魔術的な力をもつ守護精霊が棲むと考えていたようである。
英国の詩人。地主の長子としてサセックスに生まれ、イートン校に入学、もっぱら古典や社会思想・自然科学に関する読書にふける。
1810年、オックスフォードに入学、社会・政治・宗教問題に関心をいだく。
1816年、妻メアリー・ゴドウィンと息子ウィリアムとともに大陸に渡り、ジュネーヴで初めてバイロンに会う。
妻メアリーが小説『フランケンシュタイン』Frankenstein(1818年)を書いたのはこの時期である。
シェリーは『モン・ブラン』Mont Blanc(1816年)や『英知の美を讃える歌』Hymn to Intellectual Beauty(1817年)などの詩を書いているが、この詩のなかでシェリーは宇宙に偏在する精霊的存在である「英知の美」を追い求めている。
『西風に寄せる賦』Ode to the West Wind(1819年ごろ)では、西風を自在に動く精霊として、「秋の呼吸」「烈しい風」「烈しい精」と呼んでいる。
「西風」は宇宙の大霊であり、詩人の死んだ思想を歌の魔力によって朽ち葉のようにまき散らし、新しい生命をもたらす活力となっている。
これは破壊と再生の力であり、ものごとを変質させる天成の力で、古代ケルトのドルイドの輪廻思想に類似するものである。
20歳で書いた長篇詩『マブ女王』(1812年)は寓意詩で、観念的な教訓詩であり、妻の父であるウィリアム・ゴドウィンの急進的な思想と理想的世界観を盛り込んでいる。1822年、シェリー30歳の夏、イタリアのリヴォルノからレリチに向けて出航したヨット「ドン・ジュアン号」(バイロンの命名、シェリーの呼称は「エアリエル号」)が、嵐で転覆し、シェリーは海に消える。
ローマの英国人墓地にキーツと並んだ墓石には、リー・ハントの撰になるラテン語Cor Cordium(心の心)が刻まれ、その下に「身はいずくにも朽ち果てず、海の力で変えられて、不思議な宝となっている」という詩句がある。
これはシェリーが愛唱していたシェイクスピアの『テンペスト』のなかで、妖精エアリエルが歌う一節である。
シェリーの詩想の根底につねに動いていた精神は、イェイツが指摘しているように、ケルトの妖精と同種のものであり、古代ケルトの思想ドルイドに近い生命観から出たもののように思われる。このことから考えると、シェリーもまた妖精の国という異界の消息を、伝え得た詩人といえよう。
英国の詩人。ロンドンの貸馬車屋の長男として生まれた。ジョン・クラーク学院に学び、外科医の免許を得る。
初期の詩『スペンサーにならいて』(1814年)、物語詩『エンディミオン』Endymion(1817年)、『レイミア』Lamia(1819年)、『ハイペリオンの没落』The Fall of Hyperion(1819年)の他に『ギリシア古甕の賦』『ナイティンゲールに寄せる賦』など多くの優れたオードがある。
25歳の若さで胸の病いのため静養中のローマで死去する直前まで、恋人のためにスペンサーの詩句に印をつけており、スペンサーを「妖精詩人」と呼び「詩人の中の詩人」と敬愛した。
1817年肺病の療養も兼ね、ワイト島の西海岸キャリスブルックに滞在し、森と古城を眺めながら長詩『エンディミオン』(4巻)を書く。
「美しきものは永遠の喜びである」に始まるこの長詩には、若い牧羊者エンディミオンを主人公に、「美こそ真なれ、真こそ美なれ」というギリシア風の思想による「理想美」を描いている。ギリシアのラトモス山上のアルカディアで牧神パンの祭や、川の神アルフィーアスや泉の精アレシューザ、海神ポセイドン等の神々が遊び戯れる。
1819年、ワイト島のシャンクリンで『レイミア』は書かれた。ロバート・バートンの『憂鬱の解剖』(1621年)の、フィロストラトスの書いた若者メニプス・リシウスと美しい蛇女レイミアの話をもとに物語詩を書いたといわれている。
この物語の背景は、妖精王国が出現する以前のギリシアのニンフたちの世界である。
「妖精の群れが豊かな森から
ニンフやサテュロスを追い出す以前、
妖精王オーベロンの輝く王冠や笏やマントが、
森の藪や草むら、キバナクリンザクラの草地から、
木の精や牧神たちを追い払う以前の昔のこと、……」
キーツは古典の神々の世界の次に、オーベロンやティターニアが君臨する妖精界の住民たちが出現したと考えていたことは興味深い。
『情け知らぬ美しき女人(ひと)』は、中世騎士物語の世界であるが、湖の妖精に魅せられた騎士が、丘をさまようバラッドである。
魔性の恋人は、詩のなかで「妖精の子」と呼ばれ、「妖精の歌」を歌い「妖精の洞窟」に騎士を連れて行き誘惑するが、夢のごとくかき消えてしまう。
英国の抒情詩人。リンカンシャー、サマズビーの教区牧師の4男。ケンブリッジのトリニティ・コレッジに在学中、英詩で、チャンセラーズ・ゴールドメダル(総長賞牌)を受ける。
1827年から詩集を書き始め、1833年の『亡友を悼む』In Memoriamで知られ、1859年にはアーサー王を主題とした詩を書き、また『イノック・アーデン』Enoch Arden(1864年)や、『森の住人――ロビン・フッドとメイド・マリアン』The Foresters : Robin Hood and maid Marian(1892年)等、物語詩が多い。
しかし、最初から最後までリリシズムを歌い上げた詩人であり、英国田園を描く筆は素晴らしく、最も英国的な詩人である。1850年桂冠詩人となり、オルドワース邸で死去。
Idylls of the Kingは『国王牧歌』(1859~69年)と訳され、『アーサー王の訪れ』The Coming of Arthur(1859年)から『マーリンとヴィヴィアン』Merlin and Vivian(1859年)を経て『聖盃』The Holy Grail(1869年)、『アーサーの死』The Passing of Arthur(1869年)に至るまで、中世のアーサー王伝説を歌った12巻に及ぶ物語詩である。
19世紀英国の代表作家。インド生まれで1817年に帰国、多くの時代諷刺のきいた小説を書いたが、そのなかで児童文学作品といえるのは、『バラと指輪』The Rose and the Ring ; or the History of Prince Giglio and Prince Bulbo(1855年)である。
サッカレーは1853年にふたりの娘を連れイタリアに旅をしたが、ローマ在住の英国の子どもたちのために、娘たちが「十二夜」のパーティを催したのがきっかけとなっている。
そのパーティのために、もともと画家志望だったサッカレーは、滑稽な十二夜の人形の絵を描いた。その後、病床にある少女を慰めるために、この人形を登場人物とする話をつくりだしたのである。
『バラと指輪』は、フェアリー・テイルの伝統を下地にしているが、サッカレー独自の喜劇的世界である。
身につけていると人に愛される、という魔力をもつバラと指輪が持ち主を変えるたびに、引き起こす面白さが諷刺的に書かれている。
妖精の「黒い杖」Fairy Blacksticksは、妖精が生まれてきた子どもたちに、いつも洗礼を与えることに飽きてしまい、ジーリオ王子とロザルヴァ姫が生まれたときに、いたずら半分に「ちょっとした不幸」を予言してしまう。
この予言のためにジーリオは王位を奪われ、ロザルヴァも侍女になってしまう。しかし最後には妖精のはからいで、すべて元どおりになり、相愛のふたりは結ばれ、王子バルボと王女アンジェリカも結ばれて、ハッピー・エンドになる。諷刺的であるが、作品自体はおとぎ話的あるいはファンタスティックな世界である。
英国のヴィクトリア朝を代表する小説家。ポーツマス海岸近くのランドポートで生まれる。父親は海軍経理部の書記だった。
1814年に一家はロンドンに移住、後にチャタムに移った。ディケンズは幼少のころは病弱で、読書に親しんだ。6年間のチャタムでの思い出は、のちの作品の随所で語られることになる。
1822年に一家は再びロンドンに移り、ディケンズは靴墨工場で働く。この時、父親は借財不払いのために投獄されている。やがて学校に通うが、初等教育を終えたばかりで、弁護士の事務員になる。
のちに書記官になり、さらに通信員としてイヴニング・クロニクル新聞社に勤め、自分の見聞したことを記したものが『ボズのスケッチ集』である。
1836年と1837年に『ボズのスケッチ集』Sketches by Bozの拡大版『ピクウィック・ペイパーズ』The Pickwick Papersを出版して一躍有名になる。
1836年に結婚するが、22年後にはこの妻と別居している。
1837年から『オリヴァー・トウィスト』The Adventures of Oliver Twistを連載。翌年には『ニコラス・ニクルビー』The Life and Adventures of Nicholas Nicklebyを刊行。
1842年に訪米し、その翌年に『クリスマス・キャロル』A Christmas Carolを発表。以後、クリスマスものと呼ばれる短篇が、毎年クリスマスに出されるようになった。
1844年にイタリア旅行、その2年後にはスイスに旅行した。帰国後、名作『デヴィッド・カッパーフィールド』David Copperfield(1849年)や『荒涼館』Bleak House(1852、1853年)を発表。
1850年には週刊雑誌『ハウスホールド・ワーズ』を刊行するが、『魔法の魚の骨』(1856年)はこのころの作品である。
さらに長篇『二都物語』A Tale of Two Cities(1860年)、『大いなる遺産』Great Expectations(1860年)など数多くの作品を死にいたるまで発表しつづけ、国民的作家として多くの読者を獲得した。
今日の目からは児童文学者と呼べるほど、子供たちがヴィクトリア朝時代の社会に波乱万丈に生きる姿を描いているディケンズだが、彼の作品の中で一般に児童文学の中に入れられるものは、永遠のクリスマス文学『クリスマス・キャロル』と『魔法の魚の骨』であろう。
後者の作品には、フェアリー・グランドマリナという名前の妖精が登場する。幼い頃から『赤ずきん』の話が好きで、彼女に恋をしたほどというディケンズは、民間伝承を好んでおり、『魔法の魚の骨』の物語は、伝承物語の手法や決まりにしたがって書いている。
ヴィクトリア朝を代表する詩人。文学好きの銀行家と敬虔な非国教派信者の婦人とのあいだの子。学校に行かず家で勉強する。
シェリーに惹かれ、その影響下で自分の詩を書いた。病床にあったエリザベスと大恋愛の末に結婚したことは有名。イタリアのフィレンツェに住み、ヴェネチアで客死する。
鋭利な性格描写にすぐれ、それは『男と女』Men and Women(2巻、1855年)や『劇的人物』Dramatis Personae(1864年)にうかがえる。
このなかに劇的なロマンスのひとつとして、『チャイルド・ローランド、暗黒の塔に見参』Childe Roland to the Dark Tower cameがある。
蹴られたボールを取りに走ったバード・へレンは太陽のまわる方向とは反対に走ったので、エルフ王に妖精の国に連れ去られてしまう。
兄弟たちがとりかえしに妖精の丘に行くが失敗。末のローランド公子が父王の大きな魔剣を持ち、多くの困難を克服して妖精の丘にたどり着く。
3度丘を巡り3度地面を踏むと、丘が開きへレンが出てくるが、口を聞いてはいけないとの決まりを守り、ローランドは妹を救い出す。この話はシェイクスピアも『リア王』のなかで引用している。
ジョン・ラスキンは、ロンドンの富裕な酒商人を父とし、信仰ぶかい女性を母として生まれた。若くして何度も大陸に旅行し、オックスフォード大学卒業後まもなく『近代画家論』Modern Painters(1843年)の第1巻を公にして、美術評論家として世に出た。
このなかで大学時代知り合った画家ターナー J.W.M. Turner(1775~1851年)を賛美し、また後にラファエル前派運動を弁護した。
その後も『建築の七灯』Seven Lamps of Architecture(1849年)、『ヴェニスの石』Stones of Venice(1851~53年)などにおいて、ゴシック建築の素朴さ、寛大さなどを賞揚し、ルネサンス様式の堕落を非難した。
その批評態度は写実とともに想像力を尊重したが、反面宗教的、倫理的ともいえるものである。
後はPrincipality、Constancy、Contrast、Harmonyの4要素を絵画の指導原理としたが、これをユーイング夫人 Juliana Horatia Ewing(1841~85年)は児童文学を書くにあたってつねに留意したのであった。
唯一の児童文学作品『黄金の河の王様』(1851年)の初版には、リチャード・ドイルのすぐれた絵筆が黄金の河の王様を視覚化している。
キングスレイは英国のデヴォンシャーに生まれ、父は英国国教の牧師であった。
ロンドンのキングズ・コレッジとケンブリッジのモードリン・コレッジに学び、卒業後はエバースレーで牧師になり、以後死ぬまでこの地に居住した。
1844年にファニー・グレンフェルと結婚した。
1848年には処女作『聖者の悲劇』The Saint's Tragedyを執筆した。1859年にはヴィクトリア女王の王室牧師、そしてその翌年から9年間、母校ケンブリッジ大学の教授としてModern Historyを講じている。
この折、代表作『水の子』を執筆。しかしこれまでにすでにスリルに満ちた海洋冒険の物語『西行きの船よ』Westward Ho!(1855年)や、ギリシア神話を再話化した『英雄物語』The Heroes(1856年)などを書いて、子どもの読み物の作者として知られるようになっていた。そして死の2年前には、ウェストミンスター寺院の評議員となった。
このように彼は生涯を神に捧げているが、注目すべきことは、内なる信仰だけでなく、その宗教的信条を社会改革に結びつけていったことである。
彼は資本主義社会の矛盾を批判し、階級闘争を否定しながら究極では、神の愛によって社会の調和を求めようとし、いわば、キリスト教社会主義を信奉したのである。しかも聖職者のなかでも急進派であった。
こうしてキリスト教精神に基づく社会改良の夢は、彼の文学を根底から支えていたものであった。
ジーンは英国リンカンシャーのボストンに生まれる。1863年以降はロンドンに出て、ケンジントン公園近くのホランド・ヴィラ通り6番地に住む。
詩人として3巻の詩集(1871年、1876年、1885年)と『起こったこと、感じたことの詩日記』A Rhyming Chronicles of Incidents and Feelings(1850年)が有名であり、童話の作品もいくつか書いているが、『妖精モプサ』 Mopsa the Fairyが知られている。
イギリスの詩人、批評家。パブリックスクールの名門ラグビー校の校長トマス・アーノルドの子供として生まれる。ラグビー校からオックスフォード大学ベイリオル学寮で学ぶ。在学中に書いた詩「クロムウェル」で賞を受ける。
1849年に最初の詩集『さまよえる宴客』The Strayed Reveller、『エトナ山上のエンペドクレス』Empedocles on Etna(1852年)、『詩集』(1853年)などを発表するが、世間の注目をひくまでにはいたらなかった。
その後『新詩集』(1867年)を発表、ここに収録された「ドーバー海岸」Dover Beachという詩が有名になる。この詩の、19世紀の科学的・功利的な思想が発展するなかで、神秘的なものや宗教的なものが否定されることを嘆くというテーマが、当時の時代精神をよく反映している。
その後、耽美的で懐疑的・厭世的な姿勢から文明批評の傾向を強め、後半生は『批評論集』Essays in Criticism(1865、88年)、『ケルト文学の研究』The Study of Celtic Literature(1867年)、『教養と無秩序』Culture and Anarchy(1869年)、などを発表。批評家として活躍し、のちのT.S.エリオットに影響を与えた。
正式名はダンテ・ガブリエル・チャールズ・ロセッティ。英国の画家、詩人。父親はイタリアの愛国者。
D.G.ロセッティは1824年に英国に渡り、ロンドンのキングス・コレッジに学ぶ。
1842年以来絵画を学び、マドックス・ブラウンに師事する。マドックス・ブラウンやジョン・エヴァレット・ミレー、トマス・ウルナーなどとラファエル前派を結成する。
1852年からロンドンに住み、バーン=ジョーンズやウィリアム・モリス、詩人スウィンバーンと知り合う。死んだ妻エリザベス・シタデルといっしょに埋葬してしまった詩集『生命の家』を数年後に掘り出して刊行したことは有名。
「輪廻・転生」やアダムの最初の妻「リリス」などを歌い、ロマンティックで神秘的な詩風である。
1842年以後、美術に専念。《ベアタ・ベアトリクス》以下、モリスの妻ジェーン・バーデンをモデルにしたすぐれた名画を多く残す。妖精の別名でその役をする、《運命の糸を紡ぐ3人の女神》を描いた絵もある。
クリスティナ・ロセッティはロンドンで生まれ、エレン・アレインEllen Alleynというペン・ネームで兄ダンテ・ガブリエル・ロセッティとウィリアム・モリス、バーン=ジョーンズ等の文学と絵画のグループ「ラファエル前派」とともに活躍した。
「ラファエル前派」の機関紙『ジャーム』に、『夢』やその他の詩を載せたり、『誰が風を見たでしょう』Who has seen the wind?といった純な童心を歌いあげた一連の詩(1872年に童謡集『シング・ソング』に収められる)や『りんご拾い』Apple Gathererといった哀感の漂う乙女心をうたった抒情詩などを書き綴ったりして、詩人としても知られていた。
また物語集『コモン・プレイス』Common Place(1870年)なども発表している。後年には、人生に対する諦感の気持ちと敬虔な神への思いをうたった宗教詩とも神秘詩ともいえる作品を書いている。一説によれば、クリスティナには幻視を見る能力が備わっていたともいわれる。
クリスティナはまた、数多くの妖精詩をつくったアイルランドの詩人ウィリアム・アリンガムと親しく、アイルランドの妖精学者トマス・カイトリーの『妖精神話』を愛読していた。
こうした背景が、妖精の代表的な存在ともいえるゴブリンたちを詩材にとりあげる必然を生んだのだろうと推定される。
ルイス・キャロルが書いた『不思議の国のアリス』(1865年)と『鏡の国のアリス』(1871年)のふたつのアリスは、現代の児童文学の地形をすっかり変えてしまうほどの大きな出現であった。
これまでのイギリス固有のフェアリー・テールの流れとナンセンス文学の要素を合わせ含めて、以前にはみられない純粋なファンタジーの世界を作りだしたのである。
児童文学研究家であるハーウェイ・ダートンはアリスの出現は「児童文学の精神的な噴火山」であるといっている。
このふたつの物語は、最後にすべては夢だったことが明らかになる、という落ちになっている。
しかし、夢だから何でもできる、というのではなく、目前に展開される不合理な世界に、合理的な精神を持つ少女がなんとか対応しようとする混乱が面白く、現実世界への痛烈な批判にもなっている点が新しい。
ルイス・キャロル(本名、チャールズ・ラトウィッジ・ドジソン Charles Lutwidge Dodgeson)は、1832年にチェシャー州のデアズベリーで生まれ、リッチモンド・スクール、ラグビー・スクールを経て、オックスフォード大学に学び、卒業後母校の数学教師になる。
生涯、コレッジ(クライスト・チャーチ)で過ごし独身であった。そしてキャロルは少女をこよなく愛したという。
ロジャー・グリーンの伝記によると、キャロルは生来内気でやや吃音があったが、少女と一緒にいるときはそうではなかったという。
その他にナンセンスの話『スナーク狩り』The Hunting of the Snark(1876年)と妖精の姉弟の物語『シルヴィーとブルーノ』(1889年)がある。
『不思議の国のアリス』の原話は、1862年7月4日、友人のヘンリー・リデルの3人娘と彼の友人とで、アイシス川のボート遊びをしているときに語られ、末娘のアリスの頼みで本にまとめたのがこの作品である。
ふたつのアリスの物語は、「少女の夢の中の出来事」という共通した手法がとられている。不思議の国(ワンダーランド)はおとぎの国(フェアリーランド)であり、夢の国(ドリームランド)である。
さらに不思議の国にはトランプの国が、鏡の国にはチェスの世界が重なり、幾重にも架空の世界が重なっている。
アリスの作品がもつ独創性は、非合理的な夢の世界に、合理的なものの考え方をもったアリスという子どもが紛れ込むことで生じる奇妙な世界を描いた点であろう。
ウィリアム・アリンガムはアイルランドに生まれ、14歳のときから銀行で働き、のち税関吏になる。
1863年にロンドンに出て詩人リー・ハントやD.G.ロセッティ、ウィリアム・モリスらラファエル前派の詩人や画家たちと親しく交わり詩作に集中した。
『詩集』Poems(1850年)、『昼と夜の歌』Day and Night Songs(1854年)、『アイルランドのL・ブルーサムフィールド』Laurence Bloosomfield in Ireland(1864年)、『アイルランドの詩歌集』Irish Songs and Poems(1887年)などの詩集の他、『バラード・ブック』The Ballad Book(1864年)を編纂している。
『妖精の国で』(1869年)は画家リチャード・ドイルの一連の絵が「フェアリー・アルバム」として出版されるときに、書き下ろしてつけられた物語詩である。アイルランド民間伝承の容姿や性質をそなえたエルフたちが、野原の小鳥や虫たちと花や草の間で繰り広げる物語であり、リチャード・ドイルの挿絵と相まって、魅力的な世界をつくっている。
英国の詩人、工芸芸術家、社会主義者。ロンドン郊外ウォルサムストウ生まれ。オックスフォードのエクセター・コレッジに学び、エドワード・バーン=ジョーンズやD.G.ロセッティや、フォード・マドックス・ブラウンらと終生変わらぬ友情を結んだ。
彼らはラファエル以前の絵に返ることを目的としたため、ラファエル前派と呼ばれる。1857~62年の間は画家として働いた。
14世紀中期を舞台として理想生活を想像させる『地上天国』(1868~70年)を出版。1871年、オックスフォードシャーのケルムスコット・マナーハウスを買って住居とし、多数の彩飾写本(オマル・カイヤームなど)をつくった。
アイスランドのサガによる『シグルド王』The Story of Sigurd the volsung and fall of Niblungs(1876年)はモリスの詩才の絶頂を示す。染色、織物に関する実際の技術を研究し、1877年には「古代建築保存協会」を設立し、社会主義の進展を助けた。
1890年、モリスはハマースミスにケルムスコット・プレスを開き、独特なゴシック活字をつくって自作・多作、計53冊を出版した。
彼はアイスランドに2回(1871、73年)旅行を試み、のちにアイリカー・マグナソンと協力して、翻訳した北欧神話(サガ)はチョーサーとともに彼の作品に歴然たる影響を与えた。
モリスも、テニスンが不義として非難するグウィネヴィア王妃のランスロットへの愛を、『グウィネヴィアの弁明とその他の詩』The Defence of Guenevere, and other Poems(1858年)という作品の中で同情をもって描き、裁きの庭でなぜ、どのようにランスロットへ心を捧げたか、自分の愛の軌跡を弁明させている。
ジョージ・マクドナルドは詩人、小説家、評論家、随筆家、説教師など多面的に活躍したが、イギリス児童文学史上では、1860年代にチャールズ・キングスレイやルイス・キャロルとともに、ファンタジーというジャンルを確立した作家として位置づけられる。
マクドナルドは、6人兄弟の次男としてスコットランドの北、アバディーン州(現グランピアン州)のハントレーに生まれ、父方から芸術肌を、母方から学者肌を受け継いだといわれているが、8歳のときに母親と死別した体験が彼の作品に色濃く投影している。
1840年、アバディーン大学に入学し、あらゆる学問に興味をもったが、家運が傾き、働く必要が生じてカタログ作りに雇われたサーソ城の図書館で幻想的で死の憧憬にみちたホフマンやノヴァーリスなどドイツ・ロマン派の作品群と出会ったことが、文学と生涯かかわる契機となった。
1851年結婚。11人の子どもの父親となる。このころ貧乏と病気につきまとわれながら教師や家庭教師で生計をたて、1度は牧師になるが、彼の幅広い宗教観のため保守的な信者と相いれず、2度と教会からは迎えられることはなかった。
1855年、処女作『内と外』Within and Withoutという詩劇を発表、バイロン夫人から絶賛を受けた。
また、同夫人の紹介などから友人知己にも恵まれ、1858年、最初の長篇小説で大人のためのファンタジー『ファンタステス――フェアリー・ロマンス』Phantastes : A Fairy Romanceが評判をよび、翌年ロンドンのベッドフォード大学の英文学教授に招かれることになった。
1860~70年代は彼の最も充実した創作期であった。1895年『リリス』Lilithを発表して以後は沈黙したまま、長い闘病生活の末、1905年に死去した。
『ファンタステス』で主人公アーナドスとともにフェアリーランドを旅した読者は、ドイツ・ロマン派の影響下にあるとはいえ、マクドナルド独特の宗教的アレゴリーの世界につれこまれ、C.S.ルイスをはじめ多くの作家に感動を与えた。
そして子ども向けの作品を書きはじめたのは、生来の夢想的な性格に加えて、自分の文学的才能を発揮できる場が空想的な物語においてであることを認識したことによる。彼は教える合間をぬって小品を書き、子どもや学生に物語っていた。
その最初の作品が『ふんわり王女』The Light Princess(1863年)という魔女の呪いで重力がなくなってしまい、ついでに人間性にも乏しい王女の話である。奇抜な着想とユーモア、美しい文体と底に秘めた諷刺で彼の作品の中ではいちばんよく読まれ愛されてきた。
この作品と書きためていた「巨人の心」The Giant's Heart、「影」The Shadows、「金の鍵」The Golden Keyと新しく書きたした「行き違い」Cross Purposesを集めて短篇集『妖精とのおつきあい』Dealing with the Fairies(1867年)を出版した。
その他に、人間への復讐をたくらむゴブリンと、それをはばむ鉱夫の少年カーディの『王女とゴブリン』(1872年)などの3作の『王女』シリーズがある。
また少年ダイアモンドを美しい北風の精がさまざまなところに案内する話『北風のうしろの国』(1871年)や1895年にはアダムの最初の妻を描いた『リリス』があり、この世以外に住む超自然のものたちと、人間との交渉によってつくりだされる、ファンタスティックな世界を主に描いている。
ウィリアム・H・ハドソンは、アルゼンチンのブエノスアイレス近郊の小さな村に生まれ、博物学者として、また作家として活躍した。
土地の人と自然に親しんだ青少年時代の経験は、後にハドソンの博物学者としての基礎を養い、また彼の文学作品にも多大な影響を与えた。
1869年渡英し、『ダウンランドの自然』Nature in Downland(1900年)、『羊飼いの生活』Shepherd's Life(1910年)等を書く一方、『紫の地』The Purple Land(1885年)、『水晶の時』A Crystal Age(1887年)、『緑の館』Green Manshions(1904年)の3篇の小説等を著した。
生涯病弱であったが、晩年になってハドソンは植物学者としても、作家としても著名になる。ハドソンの小説は学者の作品として、また特色あるロマンス風物語として広く愛読されている。児童文学において、20世紀初頭のファンタジー作家として知られている。
『夢を追う子』A Little Boy Lost(1905年)は、ハドソンの子ども時代の回想や大草原に伝わる昔話・伝説をもとに書かれた。
蜃気楼を追って迷子になったマーティン少年が、両親に心配をかけ、親切な老人を裏切って、草原や森や山の神秘を探検する。
マーティンが放浪の途中で出会う蜃気楼の女王は、マーティンのそれまでの行動を許し、自由に地上を歩けるよう特別な加護を与える。海に出て旅を終える過程で、マーティン少年が成長してゆく冒険物語である。
『緑の館』は不思議な魅力をもつアベルから打ち明けられた過去を、親友(筆者)が語るという形式で物語はすすめられている。
アベルは南米ヴェネズエラの名門出身であるが革命に巻き込まれ故郷を去り、オリノコ河南側の未踏の地に入る。先住民の言葉と文化を理解する能力に長けていたアベルは、ある部族の村に定住をする。
集落の近くの美しい森をアベルは好んだが、先住民たちは魔性の女が住んでいると言って絶対に近寄ろうとしなかった。
アベルが毒蛇にかまれて魔性の女と呼ばれる少女リーマに助けられたのをきかっけに、ふたりは愛し合うようになる。
動物たちの言葉を解し、遠くのものを見ることができる不思議な力と美しい独自の言葉をもつリーマは、森の妖精のようである。
リーマの願いで生まれ故郷リオラマに行くが、期待していた身寄りには会えない。アベルと結婚の約束をしたリーマは一足先に自分の森に帰るが、先住民によって焼き殺されてしまう。
リーマを失ったアベルは悲しみと飢えにさいなまれながら、リーマの遺骨を手製の壺に入れて故郷に帰る。
アンドリュー・ラングは詩人、評論家、随筆家、民俗学者、歴史学者、古典学者として多方面で活躍したが、何よりもフェアリー・テイルズの作者、編纂者として著名である。
スコットランド南部の国境地方セルカークに生まれたラングは、6人弟妹をもつ長兄で、その地方に豊富に存在した伝説やバラッド、昔話を聞いて育った。
セルカーク・グラマースクール、セント・アンドリューズ大学を経て、1865年、オックスフォード大学ベイリオル・コレッジ入学、1868年マートン学寮のフェローとなる。その間レッド・インディアンものに影響されたり、『イリアス』The Iliadとの出会いやW.スコットの作品やスコットランドの歴史への没頭など、後の彼の仕事の源となる萌芽がみられる。
1863年に大学の雑誌に2つの詩と3篇のエッセイを発表したのを最初とし、1871年にBallads and Lyrics of Old Franceというフランスの古い詩の翻訳集を最初の出版書として、生涯に120冊の作品、150冊の編著、数百篇の詩、5000をこえるエッセイや論文を著す多作ぶりであった。
民俗学者であり詩人のアンドリュー・ラングは、「神話や伝説、昔話など伝承文学の根本に横たわる原始心性は同じものであり多元的に発生する」という説にもとづいて、いろいろな国の昔話を再話して、『青色の童話集』をはじめ、赤色、緑色、灰色など色分け童話集(青色詩歌集等を含めると25巻、童話集だけでは11巻、1889~1910年)を出版し、世界各国童話の集大成を成し遂げた。
また彼が翻訳し書き改めたギリシアの叙事詩ホメロスの『イリアス』や『オデュッセイア』は、現代に至るまでイギリスの子どもたちにギリシア神話を親しませる古典的存在となっている。
アイルランドの詩人で、『妖精』『レプラホーン――妖精の靴屋』など民間伝承の典型的な妖精の容姿と性質を詩に歌ったウィリアム・アリンガムの物語詩『妖精の国で』(1869年)の本に、リチャード・ドイルは挿絵をつけた。その可愛らしくコミカルな妖精たちの王国の挿絵は、妖精画の傑作のひとつであるが、民俗学者のアンドリュー・ラングはこの挿絵を見ているうちに、ひとつの物語をつくってしまった。それが『誰でもない王女』である。
『黄金の河の王様』の場合はゲルマン系のダーク・エルフで、長いひげのやや醜い小人であったが、『誰でもない王女』のドワーフたちは明るくかわいらしく、無邪気にキノコにまたがったり、睡蓮の花に隠れたり、フュッシャの花にさがって遊ぶライト・エルフである。
草原でカタツムリとたわむれ、バッタと戦い、蝶に乗って飛び、小鳥に歌を教え、昆虫や小動物たちとともに暮らす小さな妖精たちである。
ドングリの殻に隠れ、コウモリの翼から洋服をつくり、豆の花やクモの巣、からし種や蛾の君と呼ばれる『夏の夜の夢』の妖精たちと近いが、このオーベロンの妖精王国がプリンセス・ニエンテの物語の背景にあるということは、パックの登場でわかってくる。
かわいい自分の赤ん坊の王女ニエンテをそれと知らずにあげることを約束した王様の悩みを解決するのがパックであるが、このパックが自分は「オーベロンとティターニアと同じ国からきた」と言っている。
妖精王と女王の王国を描くとなると、作家や画家の頭の中には『夏の夜の夢』の世界が必ず浮かんでくることが、このことからもうかがえるようである。
しかしながら、絵画の世界から想像力を刺激され、物語をつくっていったアンドリュー・ラングの筆致は非常に詩的である。
オスカー・ワイルドは、本名オスカー・フィンガル・オフラハティ・ウィリス・ワイルド Oscar Fingal O'Flahertie Willis Wildeといい、「フィンガル」や「オフラハティ」といった独特なミドルネームでわかるように、アイルランド系の英国の詩人・小説家・劇作家・評論家である。
父親はアイルランドの首都ダブリンの眼科医で考古学者。母親はアイルランド愛国主義者の詩人であり、アイルランドの民間伝承の研究者・再話家としても著名で、「レディ・ワイルド」または「スペランザ」Speranzaという筆名でもよく知られている。
オスカー・ワイルドはアイルランドのトリニティ・コレッジ在学中から古典詩人として知られ、1872年に古典語優秀賞として金賞のメダルを受賞する。
オックスフォードのモーダレン・コレッジ終了の際、「ラヴェンナ」という詩でニューデイゲイト賞を受ける。ギルバート・サリヴァンのオペレッタ『ペイシェンス』で諷刺されたことをきっかけにアメリカに渡って講演旅行をし、その後もしばしば渡米および講演旅行を行った。
30歳の時にアイルランド講演旅行中に、ダブリンでコンスタンス・ロイドと結婚。翌年長男のシリルが、次の年に次男のヴィヴィアンが生まれる。
この2人の子供を可愛がったワイルドは、父親としてさまざまな物語を語って聞かせたが、それらは2冊の童話集『幸福な王子、その他の物語』『ざくろの家』としてまとめられた。
これらの作品と平行して小説『ドリアン・グレイの肖像』The Picture of Dorian Grey(1891年)、フランス語の劇『サロメ』Salome(1892年)、評論『意向集』Intentions(1891年)、を発表。
男色事件で世間を騒がせて2年間投獄され、出獄後『レディング獄舎のバラッド』The Ballad of Reading Gaol(1898年)、『獄中記』De Profundis(1901年)を出版。
また一連の社会風刺劇『ウィンダミア夫人の扇』Lady Windermere's Fan(1892年)、『真面目が肝心』The Importance of Being Earnest(1895年)の劇作家としても知られている。
童話は上述のように『幸福な王子、その他の物語』The Happy Prince and Other Stories(1888年)と『ざくろの家』A House of Pomegranates(1891年)の2冊の童話集の9篇。
ワイルドはケルト人(アイルランド人)独特の幻想的な想像力と機知と巧みな表現で、アンデルセン童話がもつ北欧の情趣に似た哀愁の漂う世界を作り上げ、その美と愛と哀しみを主題にしたストーリーは、子供だけでなく大人の鑑賞にも耐えうるものである。
そのうち妖精に近い登場人物がふたつあり、それが巨人と人魚であった。
『わがままな巨人』はコーンウォールの巨人伝説をもとにしているが、中世キリスト教伝説も背景にある。また『漁夫と彼の魂』The Fisherman and his Souldは、美しい人魚に愛を捧げ、身を滅ぼす漁夫の物語である。
本名はウィリアム・シャープ William Sharp、スコットランド生まれの詩人、小説家、批評家。1881年ロセッティと知り合い、このころから文筆生活に入る。
『ロセッティ』D.G.Rossetti(1882年)、『シェリー』Shelley(1887年)、『ハイネ』Heine(1888年)、『ブラウニング』R. Browning(1890年)などの評伝がある。
詩集には『抒情歌謡と幻想詩集』Romantic Ballads and Poems of Phantasy(1888年)、物語には『ジプシーキリスト』The Gipsy Christ and Other Tales(1897年)がある。
ケルト風の神秘的な情趣を湛えた作品が多く、『森のささやくところ』Where the Forest Murmurs、『バンシーその他の伝説的道徳物語』The Washer of the Ford and Other Legendary Moralities(1896年)等がある。
劇作には妖精劇『不滅の時』The Immortal Hour(1908年)があるが、これはケルト神話のダーナ神族の恋物語「ミディールとエーディン」がもとになっており、妖精の乙女エーディンが主人公である。
マクラウドはスコットランドの西の小島、聖者コロンバにゆかりのある心霊の島アイオナに滞在し、ケルト人の神話、伝説、民間伝承に根差した物語や詩を書き、滅びゆく運命をもった「ケルトの暗い哀しさ」を訴えつづけた。
アイオナ島で、マクラウドはジョージ・メレディ宛ての手紙に、自分が抱いているスコティッシュ・ケルトへの強い愛着が感じられる物語を書いた理由を、以下のように述べている。
「これらの物語には、ケルト人の深い秘密が入っています。この世の美しさ、人生の哀感、暗さ、運命感、神秘の輝き――こうしたものから生じてくるケルト人の遺産、これらを書き記したかったのです」。
女性の筆名フィオナ・マクラウドがウィリアム・シャープであることは、イタリアのシチリア島で彼が病死するまで一般には知られなかった。
英国の児童文学者。イーディス・ネズビットは幼いころ学者の父を失い、母の手で育てられ、後にフェビアン協会の創立者のひとりであったヒューバート・ブランドと結婚。
短い髪でコルセットも着けず、煙草も吸うという新しい女性で、穏健な社会主義に共鳴した。しかし夫の事業失敗のため経済的に困り、執筆するようになる。
最初、詩、小説、劇、批評などを手がけたが、40歳ごろ、子ども時代の経験をもとに物語を書きはじめ、第一次大戦の前までに、数多くの児童文学を発表した。
作品はリアリズムのものとして『宝さがしの子どもたち』The Story of the Treasure Seekers(1899年)、『よい子連盟』The Wouldbegoods(1901年)、『続宝さがしの子どもたち』The New Treasure Seekers(1904年)、『鉄道の子どもたち』The Railway Children(1906年)などがある。
ファンタジーの主な作品は『砂の妖精サミアッド』(1902年)、『不死鳥とじゅうたん』The Phoenix and the Carpet(1904年)、『お守り物語』The Story of the Amulet(1906年)などである。
『砂の妖精サミアッド』は、バスタブル家の5人の子どもが、むかし妖精海岸であった丘の砂の中から「砂の妖精サミアッド」を見つける。
この砂の妖精は1日ひとつ願い事をかなえるが、日暮れとともにその力は消えてしまう。そのくい違いに惹き起こされる事件に面白さがある。
トラヴァース、ノートン、ボストン、C.S.ルイスなどに影響を与え、いわば20世紀児童文学の源泉である。
現実の生活の中にファンタジーを確立させ、その中で子どもたちを生き生きと描いている。
ケネス・グレアムは、幼いときに母を亡くし故郷を離れた。そのころ過ごしたテムズ河畔の森や川辺での思い出は、生涯記憶に残るものだった。
銀行に勤めるかたわら執筆し、『黄金時代』The Golden Age(1895年)と『夢みる日々』Dream Days(1898年)(お人よしの竜 Reluctant Dragonはここに出てくる)で著名になる。その後、20世紀の古典といわれる『楽しい川辺』The Wind in the Willows(1908年)を発表する。
オックスフォード在学中に20歳で亡くなったひとり息子のアラスティアに宛てて出した手紙に、「可愛いネズミ君、君はヒキガエルの冒険のことを知っているかい?」と書いたことから、物語は展開し、不思議な世界に出て、さまざまな経験をするヒキガエル「トッド氏」の冒険が語られる。
自動車を見ると夢中になって、乗りたがるヒキガエルのトッド氏が、人の自動車を盗んだかどで、牢屋に入れられてしまう。その間に、家屋敷をテンやイタチどもにのっとられてしまい、それをアナグマやモグラ、ネズミたち友人の助けによって取り戻すというエピソードもある。
川辺に棲む小動物たち、ネズミやモグラ、ヒキガエル、アナグマ、イタチ、テンなどが擬人化され、空想裡に、彼らの世界が描かれている。
イギリスの小説家、劇作家であるバリは、スコットランドに生まれ、エディンバラ大学を卒業後、新聞記者になり、ロンドンに出る。『スラムズの窓』A Window in Thrums(1889年)などの小説で著名になる。
1891年ごろから一時劇作に専念するが、1896年ごろから小説を再び書きはじめる。第一次世界大戦後の人気芝居『メアリー・ローズ』Mary Rose(1920年初演)は夫と子どもとともにピクニックに行ったメアリー・ローズが、神隠しにあう。
彼女の姿を見つけられないまま25年たち、子どもは立派な軍人になる。ある日突然25年前の姿で、メアリー・ローズは現れる。彼女の中ではまったく時間が経過せず、ついさっきまで、ピクニックをしていたという。
『ケンジントン公園のピーター・パン』(1906年)、『ピーター・パンとウェンディ』(1911年)は初め『ピーター・パン――大人にならない子供』Peter Pan――Never grown up(1904年初演)という戯曲であった。
この「ピーター・パン」の戯曲の前身は、『小さな白い鳥』The Little White Bird(1902年)で、ピーター・パンの前身は小鳥、生まれる前の赤ん坊もみんな小鳥で、ネヴァネヴァランドで生まれるのを待っているという設定である。
ピーター・パンは現実と非現実の中間の領域に、架空の妖精ではなく、より人間の子どもに近い実在を備え、しかも子どもの純な状態を永遠にもちつづけている、いわば「永遠の子ども」の典型である。
アイルランドの民俗学者。『コナハトの愛の歌』Love Songs of Connacht(1894年)、『初期ゲール文学物語』The Story of Early Gaelic Literature(1894年)などの古学の翻訳および研究や、戯曲『泡の噴出』The Bursting of the Bubble(1905年)、『いかけ屋と妖精』The Tinker and the Fairy(1905年)などがある。
編著書である『炉辺にて――アイルランド昔話集』Beside the Fire. A Collection of Irish Gaelic Folk Stories(1890年)において、ハイドはアイルランド語と英語を、見開きページに対照させて載せるという体裁を用いた。この本で彼が再話した話は、妖精よりは亡霊や魔法についての作品が多い。
そのなかで「グリーシュ」の話は、妖精の飛行ならびに妖精界のとらわれ人の救出を物語っている。
ゲール語の民話の正確な英訳につとめ、「ムナハとマナハ」にみられるように、ロスコモンやゴールウェイのゲール語話者の語る言葉を、逐語的に書きとめた。
ダグラス・ハイドは、アイルランド・ゲール語の研究を促進するためにアイルランド語連盟を設立した。
また、アイルランド文芸の復興に関しては、W.B.イェイツやグレゴリー夫人の同志であり、1938年には、アイルランド共和国の初代大統領に選出された。
イェイツはハイドを「その作品から泥炭の煙が香る人たちの流れをくむ歌謡作者たちの最後のひとりといえる」と言っている。
英国の小説家、詩人。生涯、英国とインドの間を行き来したキップリングは、インドのボンベイに生まれた。
父は美術学校の校長であった。インドでジャーナリストとして活躍する一方、短篇集『高原平話』Plain Tales from the Hills(1882年)で著名になる。
日本や中国、アメリカ、オーストラリア、アフリカ等を旅行。『ジャングル・ブック』The Jungle Book(1894年)およびその続編 The Second Jungle Book(1901年)、『勇敢な船長たち』Captains Courageous(1897年)、『キム』Kim(1901年)、『プークが丘のパック』(1906年)、『ごほうびと妖精』Rewards and Fairies(1910年)などを著す。
1907年に、41歳という最年少でノーベル文学賞受賞。ウェストミンスター寺院の詩人墓地に眠っている。
アイルランド・ダブリンの郊外、サンディマウントに生まれる。幼年期、父親が画家修業でロンドンに出たので、祖父母に預けられ母方の故郷スライゴーで過ごした。「召使いが私たちの生活の、多くの部分を占めていました。彼らは天使、聖者、バンシー、妖精たちと親しくつきあっていて、よく知っており、とてもうまくいっているようでした」と姉のメリーが語るように、イェイツも「本当にたくさんの話を聞いております……世の中は、奇怪なものと不思議なことでいっぱいでした」と当時を回顧している。
召使のひとりで、字は読めないが透視力をもつメアリー・バトルや雨漏りする小屋に住む老人パディ・フリンとの出会いが、幼いイェイツの心を異教の神々や超自然のものと交流する、古代人の心の世界に触れさせたようである。
また少年期に大半を、スライゴーやバリソディア、ロセッスで過ごしたイェイツは、その土地の人々がよそ者には警戒して話さない妖精物語を、泥炭の煙のなかで語ってくれたという。
1887年に22歳のイェイツは、キャメロット・クラシックス叢書のひとつに、アイルランド民話の編集を依頼された。
クロフトン・クローカーの『アイルランド南部の妖精伝説と伝承』を復活さようとしたが版権の問題で方針を変え、アイルランドの農民や漁民のあいだに語られていた話(バーディック・テイルズ)や民間伝承(フォーク・テイルズ)を、自らの鑑識眼で選び、ときには訂正削除の筆を入れ、物語を編集し分類し、体系化に努めたのである。ここに、幼児・少年期の民間伝承採集が生かされたのは当然である。
これらは『アイルランド農民の妖精物語と民話』The Fairy Tales of the Irish Peasantry(1888年)、『アイルランド妖精物語』The Fairy Tales in Ireland(1892年)として出版された。
「アイルランドにおけるあらゆる種類の民間信仰を、一望のもとに見渡せるように努力し編集した」と言っているように、ここにはアイルランドやケルト人の深遠で神秘な魂の在り方を、垣間見させる物語の世界が広がっており、付録としてつけられた「アイルランド妖精の分類」一覧は、後世の者にとり妖精辞典の感がある。
またこの書は19世紀アイルランドの文芸復興運動(ケルト復活年)を促進させ、またイェイツ自身の文学活動の出発と源泉である。
このほか採集話の『ケルトの薄明』The Celtic Twilight(1893年)があり、詩集には『オシンのさすらい』The Wonderings of Oisin and Other Poems(1889年)から『最後の詩とふたつの戯曲』Last Poems and Two Plays(1939年)があり、戯曲には『鷹の井戸』At the Hawk's Well(1917年)、『クー・ホリンの死』The Death of Cuchulin(1892年)、『緑の兜』The Green Helmet and other Poems(1910年)等がある。
『ケルトの薄明』には自ら体験した妖精現象をさまざまに書いており、『神秘の薔薇』The Secret Rose(1897年)や『錬金術の薔薇』The Alchemical Rose(1897年)には、神智学の創始者ブラバツキーの思想の影響が見てとれ、降霊術の神秘性が描かれている。
また他方、現実面の運動にも加わり、一種の国粋主義的立場からアイルランドの神話を信じ、それに連なる「アイルランド文芸復興運動」の推進のために、戯曲をアベ劇場にかけている。
1892年にアイルランド文芸協会を設立、1899年にアイルランド国民劇場協会を設立、1923年にはノーベル文学賞受賞と、まさにアイルランドの国民作家であった。
ケンブリッジ大学のラテン語の先生であり詩人であったアルフレッド・ハウスマンの弟。
兄を書いた小説『A.E.H.』(1937年)がある。
詩人・劇作家であり、挿絵画家であった。メレディスやロセッティらの詩集に挿絵を描いた。その繊細な筆の線を活かし、叙情的な雰囲気を描出する挿絵は、一躍有名になる。
自叙伝に『予期せぬ年』The Unexpected years(1936年)がある。グランヴィル・バーカーとの合作の劇『プルネーラ』Prunella(1906年)が有名である。
英国の詩人、小説家。フランスのユグノーを祖先にもつ名門の出身。デ・ラ・メアはケント州に生まれたが、4歳のとき父を失い、母とともにロンドンへ出て、セント・ポール聖歌学校に学ぶ。 詩人ブラウニングの血筋を引き、『幼時のうた』Song of Childhood(1902年)の処女詩集以後、『孔雀パイ』Peacock Pie(1913年)を経て、最後の『ああ、美わしの英国』O Lovely England に至るまで、22冊の詩集を書いている。 小説家としても、長篇『帰ってきた人』The Return(1910年)、『小人の思い出』Memories of a Midget (1921年)、『サル王子の冒険(ムルガーの不思議な旅)』The Three Mulla Mulgars(1910年、1919年にThe Three Royal Monkeysと改題)の長篇のほか、『謎』The Riddleや『ジェマイマ』Miss Jemima、『ほうきの柄その他』Broomsticks and Other Stories(1925年)など16冊に及ぶ短篇集や戯曲など、さまざまなジャンルや作風の作品を数多く残している。 『サル王子の冒険』は、3匹のサル王子がさまざまな冒険や経験を重ねながらたどりつき、成長してゆく過程が描かれている。
詩人ブラウニングの血筋を引き、『幼時のうた』Song of Childhood(1902年)の処女詩集以後、『孔雀パイ』Peacock Pie(1913年)を経て、最後の『ああ、美わしの英国』O Lovely England に至るまで、22冊の詩集を書いている。
小説家としても、長篇『帰ってきた人』The Return(1910年)、『小人の思い出』Memories of a Midget (1921年)、『サル王子の冒険』(ムルガーの不思議な旅)』The Three Mulla Mulgars(1910年、1919年にThe Three Royal Monkeysと改題)の長篇のほか、『謎』The Riddleや『ジェマイマ』Miss Jemima、『ほうきの柄その他』Broomsticks and Other Stories(1925年)など16冊に及ぶ短篇集や戯曲など、さまざまなジャンルや作風の作品を数多く残している。
『サル王子の冒険』は、3匹のサル王子がさまざまな冒険や経験を重ねながら、成長してゆく過程が描かれている。
英国の作家エレノア・ファージョンの父は作家、母は俳優で、家には多くの本があり、幼いころに読んだ伝承やフェアリー・テールズの世界が、ファンタジーを書くもとになった。
1903年、父が死去し、経済的な困難から作家を志すが、作家として認められるようになるのは35歳のときからであった。『リンゴ畑のマーティン・ピピン』Martin Pippin in the Apple Orchard(1921年)、『年とったばあやのお話かご』The Old Nurse's Stocking Basket(1931年)、『イタリアののぞきめがね』Italian Peepshow(1925年)、『ヒナギク野のマーティン・ピピン』Martin Pippin in the Daisy-field(1937年)などを発表。1955年には作者自選による短篇集『ムギと王様』The Little Bookroom(1955年)でカーネギー賞を受け、同年には第1回国際アンデルセン賞作家となった。
『銀色のシギ』The Silver Curlew(1953年)はイギリスの民話「トム・ティット・トット」を題材にしている。
ノーフォークの海の近くに姉ドルと妹ポルが家族と住んでいた。ある日、ポルはチャーリーに魚をもらいに海辺に行く。黒い獣に襲われている銀のシギを助け、家で看病する。
ドルは母親が出かけたあいだにダンプリングを12個食べ、通りかかった王に母親は困って、麻糸を12かせ紡いだと答える。
麻糸を紡ぐ娘を花嫁に探していた王は、城の麻を30分で紡ぎ、1年に1度城中の糸を紡ぐことを条件にドルに結婚を申し込む。
困っているドルの前に黒いゴブリンが現れ、麻を紡いでやるから1年後に自分の名前を9度で当てろ、できなければ自分のものになれと言う。
ドルは王と結婚し、王女も誕生する。1年後ドルは糸を紡げず困っていると、ゴブリンが現れるが名前を当てられない。
ドルは妹のポルに事情を話し、チャーリーの助言と銀のシギの助けで、魔の森でゴブリンを見つける。名前を聞き出そうとするが成功せず、ポルは殺されそうになり、チャーリーに助けられる。
ふたりは木に縛られ、勝ち誇ったゴブリンは、自分の名前はトム・ティット・トットだと告げ、王女とドルを手にいれようと城に向かう。
銀のシギに助けられたポルは間に合い、名前を当てられたゴブリンは消えてしまう。ドルが糸を紡ぐことは苦手だと知った王は、強要しなくなる。
銀のシギは真夜中の妖精として、ポルの前に現れ、月の男であったチャーリーとともに空に消える。
A.A.ミルンはロンドンに生まれケンブリッジで学び、卒業後、諷刺雑誌として名高い『パンチ』誌の副編集長となる。劇作家としては『お姫さまと木こり』The Princess and the Woodcutter(1918年初演)、グレアムの作品を劇化した『ヒキガエル邸のヒキガエル』Toad of Toad Hall(1929年)が有名である。
最初の長篇『昔、ある時』Once Upon A Time)1917年)や『ぼくたちが幼かったころ』When We Were Very Young(1924年)と『6歳になったぼくら』Now We Are Six(1927年)のふたつの幼年詩集がある。
『クマのプーさん』(1926年)と『プー横町にたった家』(1928年)で有名なぬいぐるみの熊のプーは、この幼年詩集にも姿を見せていた。
クリストファーロビン少年とぬいぐるみの動物たちが活躍する世界であり、ユーモアあふれる物語である。
1925年、英国南東部イースト・サセックス州ハートフィールドにミルン一家が、当時5歳だったクリストファー・ロビンを連れて引っ越してきた。この「コッチフォード・ファーム」の敷地には、幹が空洞のクルミの大きな木があり、これがロビン少年とプーの隠れ家になった。
物語の中で登場人物たちが、木の中や木の上で過ごす時間が多いのは、実際にそういう背景だったからだ、とミルンは自伝で語っている。ミルンの家から2キロ離れたところに物語の舞台、アッシュダウンの森があり、「プーの棒投げ橋」が架かる小川が流れている。
ミルンの詩には「部屋の隅にブラウニーがいた」という詩『ブラウニー』もあり、妖精など空想の生き物にも、興味を示していたようである。
詩人であり、児童文学者、哲学者。オーストラリアに生まれロンドンで没する。イギリスで女優となるが、舞台を退き創作家になり、とくに児童文学『メアリー・ポピンズ』(邦題『風に乗ってきたメアリー・ポピンズ』)(1934年)で一躍有名になる。
メアリー・ポピンズは乳母であるが、銀ボタン付きの青い上着に麦わら帽子、おしゃれでつんとすまし、うぬぼれも強く恋もする乳母として、オウム柄付きの傘を広げ、どこからともなく東風にのって空からやってくる。
子どもたちにフェアリー・テールを語って聞かせるだけでなく、大人たちにはわからないフェアリーランド、木や風、月や光や小鳥たちと自在に交流し、お皿の風景の中で遊べるという異次元の国へ連れて行ける子どもの夢の美しい案内人ともいえよう。
続編に『帰ってきたメアリー・ポピンズ』Mary Poppins Comes back(1935年)、『扉を開けるメアリー・ポピンズ』Mary Poppins Opens the door(1943年)、『メアリー・ポピンズABC』Mary Poppins From A-Z(1962年)などがある。
詩人としてはジョージ・ラッセルに認められ、アイルランドの詩人たちと親交があった。
哲学的随想を集めた『蜂は何を知っているか』What the Bee knows?という随想集もある。
トールキンは、南アフリカのブルームフォンテンに生まれ、3歳のとき英国に移住し、オックスフォード、エクセター・コレッジを卒業。第一次世界大戦従軍後、リーズ大学の英語学教授、のちにオックスフォードのモートン・コレッジ教授になり、中世英語英文学の専門家となり、生涯のほとんどをオックスフォードで暮らした。
1925年、オックスフォード大学アングロサクソン語の教授に選ばれる。また、このころC.S.ルイスとの交流が始まる。2人はともに「インクリングズ」Inklingsという非公式の文学討論集団のメンバーだった。
1972年にCBE(名誉大英勲章第三位)を受ける。初期の編著に『ベーオウルフ――怪物と批評家たち』Beowulf : The Monsters and the Critics(1937年)、『ガウェーン卿と緑の騎士』Sir Gawain and the Green Knight(1925年)等がある。
また後年には『農夫ジャイルズの冒険』Farmer Giles of Ham(1949年)、『ニグルの木の葉』Tree and Leaf(1964年)、『星をのんだ鍛冶屋』Smith of Wootton Major(1967年)、『トム・ボンバディルの冒険』The Adventures of Tom Bombadil(1962年)など、中世を舞台に竜(ドラゴン)や巨人退治を主題にした一連の超自然的冒険物語を書いている。
『ホビットの冒険』The Hobbit(1937年)と『指輪物語』The Lord of the Rings(1954~55年)は現代妖精王国物語の傑作といえる。
『ホビットの冒険』は、トールキンの創造した小人の一種ホビット族のビルボ・バギンズが、魔法使いガンダルフと12人のドワーフとともに、竜スマウグに奪われたドワーフの宝を取り返す旅に出る。途中、山の下に住むゴクリの持つ、指にはめると姿が消える指輪を偶然手に入れ、その指輪を駆使し、数々の危機を切り抜けて目的を果たす冒険物語である。
この作品の続編『指輪物語』(『旅の仲間』The Fellowship of the Ring、『二つの塔』The Two Towers、『王の帰還』The Return of the King)では、ビルボが手に入れた指輪は、世界征服をたくらむ冥王サウロンがつくった、19個の指輪を統べる魔力の源、ひとつの指輪であることがわかる。
サウロンが指輪を探していることを知ったガンダルフは、ビルボにその指輪を甥のフロド・バギンズに渡すようにうながす。
フロドは指輪を滅ぼす旅に出る。サウロンの刺客から逃れながら指輪を滅びの山に投げ入れ、消滅させることに成功する。
この旅と同時に、サウロン率いるオーク軍と、人間・エルフ・ドワーフの連合軍とが戦い、連合軍側が勝利をおさめる。この戦いは「指輪戦争」とも呼ばれる。
トールキンは中世英文学の幅広い知識から、古代・中世の世界に棲む超自然の妖精や怪物に命を与え、ルーン文字を復活させるなど、独自の神話体系をもつ世界を構築した。
『指輪物語』完成後、この物語の前史ともいえる『シルマリリオン』The Silmarillion(1977年)を、トールキンは死に至るまで書きつづけ、死後は息子のクリストファー・トールキンが完成させ出版された。
L.M.ボストンは英国ランカシャーのサウスポートに生まれるが、11歳のとき母親が病気になり療養生活のため、田舎に移る。
パリの女子専門学校に学んだ後、オックスフォードに入学する。卒業後はロンドンのセント・トマス病院で看護士になり、第一次大戦中はフランスの病院で戦傷兵の看護にあたる。
1917年結婚。後に離婚し、一時期ヨーロッパに渡るが、1939年英国に帰国する。『グリーン・ノウ物語』Green Knowe Novels(1954~76年)の舞台となるイングランド中部のへミング・フォード・グレイの村の屋敷を購入する。
60歳を過ぎて作家活動を始め、子どものためのファンタジー『まぼろしの子どもたち』を書く。その後『グリーン・ノウ物語』の第一作『グリーン・ノウの子どもたち』The Children of Green Knowe(1954年)を書き、続いて『グリーン・ノウの煙突』The Chimneys of Green Knowe(1958年)、『グリーン・ノウの川』The River at Green Knowe(1959年)、『グリーン・ノウのお客さま』A Stranger at Green Knowe(1961年)(カーネギー賞受賞)、『グリーン・ノウの魔女』An Enemy at Green Knowe(1964年)、『グリーン・ノウの石』The Stones of Green Knowe(1976年)を著している。
ノウ Knoweはスコットランドで「丘」という意味である。その他にコーンウォールの海を舞台にしたふたりの少年と海神トリトンとの友情を描いた『海のたまご』The Sea Egg(1967年)がある。
『グリーン・ノウの子どもたち』は、曾祖母の住む古い屋敷グリーン・ノウで休暇を過ごす7歳の少年トーリー(トーズランド)の物語である。屋敷や古い石像のある広い庭は神秘的な雰囲気をもっており、トーリー少年はそこで暮らすうちに、数々の不思議なことに出会う。
昔、この家に住んでいた300年前の幻の子どもたちと知り合って遊ぶようになり、「グリーン・ノウの伝説」を知るなかで、自分の生きている現在の世界がいかに過去とのつながりをもっているかを知るようになる。作品自体、詩的な美しさをもっている。
ブライトンの経歴は、学校の教師から始まり、後にジャーナリズムに切り替わる。しばしば教育に関して筆をとるようになるが、まもなくして、児童書を書き始める。
そのブライトンの最初の本は、子ども向けに編んだ詩の本である。第二次大戦のころ、1930年ごろから「ノディ」というオモチャの人形を主人公にした『ノディ』Noddyシリーズを出す。
主人公は木の動く人形で、トイ・タウン(おもちゃの町)に住んでおり、いつも「ビッグ・イヤー」の助けを求め、「ノーボディ」に支えられながら、山にいる悪いゴブリンたちと戦ったり、凧あげや棚作りにひとりで挑んだりして、次第に学び成長していく話であり、そのピノキオのような特色あるかわいいキャラクターから、テレビ番組でも人気のシリーズのひとつとして、現在(2008年)もテレビ放送されており、本の形で『ノディさん、自分でおやりなさい』Do-It-Yourself Noddy、『ノディと魔法のバグ・パイプ』Noddy and the Magic Bagpipe、『魔法の粉』The Magic Powderなど10種類ほど出ている。
またクリスマス・シリーズ、『フェアリーのクリスマス・パーティ』The Fairies' Christmas Party、『クリスマスでのお願い』A Christmas Wish、『すべての道はサンタ・クロースへ』All the Way to Santa Clause、『子兎の最初のクリスマス』Bunny's First Christmasなど4冊セットにして同じ装丁で、イギリスの本屋で売られている。
このほかコレクターに喜ばれる、キャラクターをつくりあげ、物語や商品として成功したのが、『ゴリー』Gollyという黒人人形を主人公とした作品シリーズである。
会社ジャクソン・ジャムと提携し、賞品人形として一世を風靡し、骨董品コレクターの間で人気がある。このほか、『有名な五人』Famous Fiveや、『秘密の七人』Secret Sevenなど、少し年上の子どもを主人公にした冒険物語でも知られる。
また、『マロリーの塔』Malory Towersとか『馬鹿な娘さん』The Naughtiest Girlなど、大きい子ども向けの物語も書いている。
しかしエニッド・ブライトンには、読者を教育しようという気持ちがあり、行いの良い悪いに対する判断を、読者に持たせたいという意図が、物語の中に見え隠れしている。
したがってこれらの物語は、多くの子どもに歓迎されたが、一部の大人や図書館の人たちからは、筋書きが単純である、書き方や説明が簡単すぎて平板である、との声が挙がっている。
ルイスは北アイルランドのベルファストに生まれ、モルヴァーン・コレッジの特待生になるが退学。第一次世界大戦に参戦し負傷する。
除隊後オックスフォード、ユニヴァーシティ・コレッジで学び、1925年そのカレッジの講師およびモーダレン・コレッジのフェロー(特別研究員)に選ばれ、29年間この職を勤め、生涯の大半をオックスフォードで過ごす。
その後ケンブリッジ、モーダレン・コレッジの教授にもなる。1952年ルイスの作品に感動して文通していたアメリカ人のジョイ・デヴィドマン・グレシアムの英国滞在許可取得のため、1956年ジョイと書類上の結婚をし、翌年に正式に式をあげる。
1960年ジョイは左足の骨肉腫によって死去、3年後にルイスは65歳の誕生日の1週間前に心臓発作で他界する。
1926年モーダレンの居間に集まったトールキン、ダイソン、バーフィールドなど学者、作家、詩人たちとつくった「インクリングズ」の会は有名で、今日も存続している。
中世英文学者として教鞭をとるかたわら、キリスト教の説教講話や礼拝説教を行い、また詩人、作家、批評家としても活躍した。
アレゴリーを主題にした作品が多く、『愛の寓意』The Allegory of Love(1936年)や『大いなる離婚』The Great Divorce ; A Dream(1946年)、『奇蹟――信仰の論理』Miracles ; A Preliminary Study(1947年)、『喜びのおとずれ』Surprised by Joy, The Shape of My Early Life(1955年)などを著す。
またこの他、惑星(異界)間の出来事を描いた『マラカンドラ――沈黙の惑星を離れて』Out of the Silent Planet(1938年)や『ペレランドラ――金星への旅』Perelandra ; Voyage to Venus(1953年)など「神学的SF」ともいえる作品を書いている。
トールキンの古代の世界への指向に対し、ルイスは古典的な世界に関心があったようで、ギリシアや北欧の神話の動物たち、フォーンやドワーフ、ユニコーンやニンフたちが棲むナルニアという架空の国を創造している。巨人や人魚のほか、マーシュやティガーズなどルイスが創案した生きものも登場する。
ナルニア国物語の背景にはキリスト教的宇宙観があり、ルイスの幼児期に慣れ親しんだ物語や伝承と、のちに研究対象となった神話や中世ロマンスへの深い知識とが混然となって生まれた世界といえよう。
この物語は子ども向けに初めから書かれたものではなく、「児童文学が自己表現にもっとも適したものであるからこのジャンルが選ばれた」と『児童文学の3つの書き方』On Three ways of writing for children(1952年)の中でルイスは語っている。
メアリー・ノートンは医師の娘としてロンドンに生まれ、幼児期をベッドフォードシャーのライトン・バザードで過ごす。寄宿学校を卒業してオールド・ビッグ座のメンバーになり、端役を2、3やって結婚して、舞台を退いてしまった。
海運業の夫とともにポルトガルで過ごし、第二次大戦直後にニューヨークに渡り、1943年に英国に戻って、以後ずっと英国で過ごしている。男女2人ずつ、4人の母親である。子どもたちに話して聞かせた物語を1945年に『魔法のベッド 南の島へ』The magic bed-knobと題して出版し評判となる。
1947年にはこの続編の『魔法のベッド 過去の国へ』Bonfires and Broomsticksを出している。
ノートンは近視だったのでいつも足元を見ており、土手の草むらがいつのまにかジャングルに変わり、小人たちが活躍している姿を想像していた。
また、家の中でヘアピンや安全ピン、針や指ぬきなど、小さいものがなくなるのが不思議で、きっとこれは家のどこかにいる小人たちが持っていくのだと考えたりしたことが『借り暮らしの小人たち』(邦題『床下の小人たち』)(1952年)をつくりだす動機となったと語っている。
1952年に『借り暮らしの小人たち』は出版されたが、それ以後に『野に出た小人たち』『川を下る小人たち』『空をとぶ小人たち』『小人たちの報復』と書きつづけ、5部作として完成した。
これらの代表作で新しい小人族をつくりだしたわけだが、文明批評の面もあり、借り暮らしの小人たち Borrowersは小人のアリエッティに言わせると、人間の家の一部なのだから上の物を床下で使っても当然であり、これは「借りる」borrowingであって、「盗む」stealingとは違う。しかも、人間は「バターのためにパンが存在する」ように"Borrowers"のために存在し、生活の必需品を生産提供してくれる奴隷なのだ。こうした考え方は、人間中心の思考の回路を変えた1つの人間批判になっていよう。
父親ポッドは靴屋で、これは妖精の踊り減らした靴を片方だけ直すアイルランドの妖精、レプラホーンの系統を引いている。
ノートンはそうした妖精たちの属性を独自のものにつくり変えた。従来、超自然的な魔法の力はもたず、人間のミニチュア版になっており、その小さいというハンディキャップを背負った人間が勇気や工夫でそれらを乗り越えていく物語になっている。
デニス・ジェイムズ・ワトキンズ=ピッチフォードはBBという雅号で知られた作家であり、画家である。
1905年にノーサンプトンシャーのランポートで生まれた。双子の兄弟ロジャーとともに学校には行かず、家庭内で父親から教育を受ける。
1928年にはノーサンプトン芸術学校に進んで資格を得て、ラグビー校の美術助手を16年勤める。1939年シシリー・アドニットと幸福な結婚をし、1男1女をもうけるが、男の子ロビンを8歳にして失う。
1937年ごろより文筆をはじめ、1942年に、ブリテン島の最後の生き残りのノームを描いた『小さな灰色の人たち』(邦題『灰色の小人たちと川の冒険』)を出し、カーネギー賞を取る。
『潮の終り』Tide's Ending(1950年)、『暗い河口』Dark Estuary(1952年)が続いて出される。1974年に不明の病のため、突然に妻を失う。
1989年、バッキンガム宮殿にてMBE(名誉大英勲章第五位)の勲章を受ける。1990年、オックスフォードで死去する。
彼の作風は簡潔で、自然の中で魚を捕り、狩りをして生きる小人たちを静かに描いており、幼年時代のノーサンプトンシャーでの生活環境が、良い影響を与えているのであろう。
ダールはノルウェー人の両親の間に、ウェールズで生まれる。英国の学校で教育を受け、18歳で「シェル石油会社」に勤務する若い商社マンになった。
生涯は、まるで小説のように波乱に満ちている。初めはアフリカ支店に派遣され、そこで野生の動物のような、気ままな冒険的日常を送る経験をする。
1939年に英国がドイツに宣戦布告すると、志願して、RAF(英国空軍)の空軍兵となる。西アフリカに飛ぶが、西の砂漠の真ん中で墜落し、飛行機が炎上して頭部に負傷し、傷が治るとすぐにギリシアやシリアに飛ぶことになる。1943年にはアメリカ合衆国に派遣される。
第二次大戦後、ダールは退役して、バッキンガムシャーのリンゴ園で働きながら、小説を書きはじめる。初期には大人向けの物語を書き、後期になると子ども向けの童話を書くようになる。
童話には、『チャーリーとチョコレート工場』(邦題『チョコレート工場の秘密』)(1964年)、『魔法のゆび』The Magic Finger(1966年)、『へそまがり昔話』The Revolting Rhymes(1982年)、『魔女がいっぱい』The Witches(1983年)等があり、1980年には児童文学者として有名になる。
『魔法のゆび』は、E.T.のように、右人差し指から不思議な光が射して、それで人の性質が変えられる力をもつ、8歳の女の子の魔法物語である。
グレイグ氏一家、夫人とウィリアム(11歳)にフィリップ(8歳)というふたりの男の子の4人家族は、鴨猟が好きで得意であり、鉄砲でよく鴨を撃ち殺して食べていた。
ところがある日のこと、この女の子の右人差し指の不思議な光に当たり、一家は鴨に変身してしまい、空を飛んだり、木の上に巣をつくったりする。
一方、鴨のほうは人間の大きさになって、家の台所で料理をしたり、オモチャで遊んだりする。鴨と人間の、位置と役割の入れ替えである。
そこで鴨はクレイグ一家がするように狩りに行き、クレイグ一家に鉄砲を向けると、クレイグ氏は鴨に命請いをする羽目になる。グレイグ一家の改心は言うまでもない。
『チョコレート工場』の物語にも、超自然の魔法が使われており、経営者のウィリー・ウォンカ氏と、チョコレート工場の工員ウンパルンパたちは、みな小人の妖精で、そこに来た見学者の5人の人間の子どもたちと、次々と騒動が持ち上がる物語である。
続編の『チャーリーと巨大なガラスのエレヴェーター』(邦題『ガラスのエレベーター 宇宙にとびだす』)Charlie and the Great Glass Elevater(1973年)のほか、『ジェイムズと巨大な桃』(邦題『おばけ桃の冒険』)James and the Giant Peach(1961年)、『とても大きく親しい巨人』The BFG(1982年)等もあり、小人や巨人と人間が絡み、人間と昆虫が口をきき、魔法が功を奏する不思議な物語が多い。
アラン・ガーナーは英国の現代作家であり、出生地のコングルトンのあるチェシャーの土地と文化に、その言葉使いも主題も二重に拠っている。
30冊ほどの著書があるが、その多くは子ども向けのファンタジー・フィクションであり、初めに書いた『ブリジンガメンの魔法の宝石』The Weirdstone of Brisingamen(1956年)は、22歳のときの作品である。『ふくろう模様の皿』The Owl Service(1967年)でカーネギー賞を獲得している。
このほか、『ゴムラスの月』The Moon of Gomrath(1963年)、『レッド・シフト』Red Shift(1973年)、『雷鳴の声』The Voice of that Thunders(エッセイ・講義録)などがあり、「ガーディアン子ども創作賞」を獲得している。
その作風は非常に神秘的・歴史的であり、ウェールズの古い伝承物語と現代の話とを、上手に混じり合わせた物語が多い。
『ブリジンガメンの魔法の宝石』では、スーザンとコリンが魔法使いカデリンに会い、150人の騎士のいる洞窟を訪ねるが、みな善の力を発揮するときがくるまで、白い馬とともに眠っている。悪い魔女モリガンが、スーザンの持つムーンストーンを狙い、奪おうとして戦いが起こる。アラン・ガーナーはオックスフォード時代に、学寮でJ.R.R.トールキンやC.S.ルイスに会っており、彼らと同じように、超自然の世界を、伝説的なフォークロアを生かしながら描いている。
主にウェールズに伝わるケルトの伝説物語『マビノギオン』とアーサー王伝説が、彼の物語のもとにある。直接には、ロバート・グレーヴズに負うところが多い。
アランはこう言っている。「学べば学ぶほど、次のようなことを確認するにいたった。すなわち独創的な物語など根源的にはまったくなく、いわばブリテンのフォークロアにある主題と、表現された豊かなものとを、個人的に色づけするだけである。
この非常に豊かなものとは、映像的にも豊かであり、こうしたことを理解しようとするなら、学問的やり方が必要となってくる」。
こう言うアランの言葉には、彼の創作の根源的な秘密が隠されていよう。長年にわたり児童文学を書きつづけた功績により、2001年にOBE(名誉大英勲章第四位)を授与されている。
ユダヤ系の父と英国人の母との子で、世界に数百の支店を持つ「マークス・アンド・スペンサー」の重役。
実務は他の人に任せ、童話の創作や絵画製作に没入。『黄金のりんごの王子』を著す。
ポンプシーナという猫を使い魔に使っている魔女に歌声を奪われた小鳥たちを、湖の精や木の葉の精(グリング)、りんごじいさんなどの助けを借りて解放し、自然の歌を取り戻す話である。
現代英国の年長少年のための童話、幻想的で神秘的な「デスク・ノヴェル」と呼ばれる一連のファンタスティックな世界を作品に書く作家として、英国ではよく知られている。
17歳のときに書き下ろし、45歳で加筆し完成させ発売した作品『カーペットの住人』The Carpet People(1971年)が、広く読まれベストセラーになる。
カーペットの中に各種の民族、いろいろな人々が住んでおり、ドゥミー族という帝国の建造物をつくった者から、マンラング族や誇り高きデフトメン族、そこに押し寄せる未開の地からやってきた生き物たちと、各種族の間で闘争がくり広げられる。
『小さな自由人間』The Wee Free Men(2003年)では、「ナック・マッグ・フィーグル」Nac Mac Feegleという小人の妖精族をつくりだした。彼らは酔っ払いで散らかし屋のためにフェアリーランドから追い出された小さな青いピクシー族といつも喧嘩をしている。その妖精の女王が、エイキング家のティファニーの弟をさらい、ティファニーは「フライパン」とおばあさんの「魔法の本」を武器にして、弟をとり戻す話である。
「波の底の国」とか「ジェニー・グリーンティース」「箒に乗った魔女」など伝統的なアイルランドや英国の妖精物語が意識的に使われている。
この小人族の物語は、テイト・ギャラリーのリチャード・ダッドの絵画《妖精打者の最後の一撃》から思いついたと著者の付記にある。
この他、『魔法の色』The Colour of Magic、『明るいファンタスティックな物語』The Light Fantastic、『平等の儀式』Equal Rites、『魔術師』Sourcery、『魔法を使う女たち』Wyrd Sisters、『ピラミッド』Pyramidsなど、超自然の魔法でこの世と違う世界をつくりだして、その世界で人々を活躍させる物語が多く、『交易する人々』Truckers、『掘る人々』Diggers、『飛ぶ人々』Wingsのブロムリアード3部作と呼ばれる作品群は有名であり、映画にもなっている。
ユーモラスな科学フィクションとしては、『ストラタ』Strata、『太陽の暗黒面』The Dark Side of the Sun、『良い前ぶれ』Good Omenなどがある。
サマセット州からウィルトシャー州に移り住み、その広大な庭に面白い植物を栽培しながら、4人の子どもたちを育て、作家として執筆に専念。
1998年OBE(名誉大英勲章第四位)を受賞。
英国南西部ブリストル近くの小さな町チッピング・ソドベリー生まれ。エクセター大学卒業後、英語教師をしていたが、ポルトガル在住結婚、一女ジェシカが生まれたが、夫との不和でジェシカを連れて離婚。
イギリスでシングルマザーとして生活保護を受けながら生活。エディンバラの一カフェを書斎代わりにして書き上げた童話『ハリー・ポッターと賢者の石』(1994年)が当時のファンタジーブームに乗り成功。ブルームズベリー出版社から出て、児童文学として高く評価され、多くの外国語に訳され世界的ベストセラーとなる。
連作として1998年に『ハリー・ポッターと秘密の部屋』を出版。児童文学に新たな地平線を切り開いた。
第3作続編は『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』(1999年)、『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』(2000年)でOBE(名誉大英勲章第四位)を受賞。
翌年2001年に再婚。『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』(2003年)、『ハリー・ポッターと謎のプリンス』(2005年)、『ハリー・ポッターと死の秘宝』(2007年)とハリー・ポッターシリーズは書きつづけられ、映画化され世界的に評判になっている。
2000年に母校エクセター大学で名誉博士号を授与された。
|
| (井村 君江【著】「妖精学大全」より) |
|